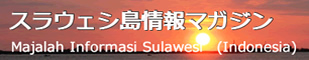 総目次 総目次 |
大航海時代とマルク諸島(2)
香料群島へ・・・ポルトガルの航跡
北スラウェシ日本人会
長崎節夫
① エンリケ航海王子とサグレス岬
ポルトガルは15世紀初めにジョアン1世がアヴィス王朝をうちたてて国の基盤がほぼ固まったあと、王室主導で海路による東洋への進出を図った。狙いは香料の産地直接取引きである。要するに貿易立国を目指したのである。ジョアン1世の第3王子エンリケが脚本兼プロデューサーをつとめ、父王ジョアン1世ほか兄弟王子たちはチームワークよくエンリケ王子を援護した。王子の背後にいるキリスト騎士団は強力なスポンサーとなって、資金面で王子の探検事業を支援した。イベリア半島の小国ポルトガルは、エンリケ王子ほか関係者一同の奮闘努力によって“16世紀はポルトガルの世紀”と称されるほどの繁栄を極めた。王子がこの世に生きた のは14世紀末から15世紀なかばまでの66年間であった。今、彼の事績をふり返って見ると、エンリケ王子はポルトガルを海洋強国に仕立てるために天から降りてきた人物であったように思える。
1416年(王子22歳)、北アフリカ・セウタの遠征から戻って間もない頃、エンリケ王子はポルトガルの南西端サグレス地方に領地を所望した。彼は拝領した領地(サグレス岬の付け根一帯)を、自身の趣味と国家の実益を合致させる事業の拠点として仕立て上げた。現代風のイメージとして言えば、一人の船オタクがサグレス岬一帯を海洋技術系大学のキャンパスに仕立てあげたというところであろうか。
キャンパスと言っても、私たちが普通にイメージするように大学の看板が出ていたり、学部の建物や管理棟などを整えたということではなかった。村の中の適地に必要な規模の講堂や倉庫を建てたり、あるいは既存の民家を利用したのかもしれない。教授陣も学生も必要な分野の人材を必要員数だけ招集して、与えられたテーマを追求した。学生はほとんど現役バリバリの船乗りたちが必要な員数だけ招集された。その意味では大学というより海事専門の研究所または訓練所と言うのが妥当かもしれない。
いつしか地域の住民は、サグレス村一帯を“王子の村”あるいは“航海学校”とよぶようになり、21世紀の現代では(実態は無くなったが)伝説だけが残っている。
サグレス岬はイベリア半島の南西端から大西洋に向かって突き出している。その突き出した岬の中ほどに“砦の跡”というのが現在も残っていて、観光資源として活用されている。それが本当にエンリケ王子の時代に存在したものか、あるいはそれ以後の建造物なのか、どうであろうか。もし、エンリケ王子にまつわる伝承(あるいは伝説)を三次元の映像として映し出すことができるならば、現在砦の跡とされている場所あたりに天体観測施設(天文台)を見ることが出来るに違いない。王子が造ったとされる“天文台”や“航海学校”は今では何の実態もない伝説になっているが、現地の空気感というか雰囲気というのは、この伝説が事実にもとづくものであることを十分に感じさせてくれている。
岬のふもとには集落があり、その脇に小さな川が大西洋に流れ出ている。その河口付近に船溜まりを築造し、砂浜を造船所とした。ここで探検船の設計から建造、実証試験までおこなわれた。造船用木材は村の北・東方に広がる山林から切り出され、川を利用して運ばれたであろう。また、船員を選抜・招集して再教育を施し、あるいは彼らの知見をくみ上げて海事技術の底上げを図った。航海用地図の精度向上には当然ながら意欲的で、実際に次から次に送り出している探検船隊の観測データを収集して地図作成に反映させた。
( * 現在、サグレス岬・サグレス村一帯に王子の活動の痕跡が残っていない理由ははっきりしている。一つは1587年の人為的破壊(イギリスの海賊提督ドレイクの破壊活動)で、あとの一つは1755年のリスボン大地震による破壊である。
ドレイクはエンリケ王子の時代からおよそ100年後の英国の王室(エリザベス1世)公認の海賊で、世界中の海を荒らし回り、略奪した莫大な財宝を王室に上納した。1587年のサグレス襲撃ではエンリケ王子ゆかりの施設が徹底的に破壊されたと言い伝えられている。
それからさらに200年後のリスボン大地震では、波高30メートルの津波がサグレス村を襲った。ドレーク襲撃の際に残された遺構があったとしても、たぶん、この津波できれいに掃除された)。
1420年5月、26歳のエンリケ王子はキリスト教騎士団の指導者に任命された。キリスト教騎士団は国家の枠をこえたカトリックの団体で豊富な資金源を持っており、エンリケ王子の探検事業の支えとなった。王子は15世紀半ばの1460年享年66で没したが、ポルトガルの探検事業(=東洋航路の開拓事業)は王室に引き継がれ国家事業として継続した。
エンリケ王子の時代、アフリカ大陸西岸から南岸一帯はヨーロッパ人にとってほとんど未知の領域で、船乗りにとっては妖怪・魔物が幅を利かせている迷信の世界でもあった。船乗りたちにとっては、想像もつかないはるか彼方にあるインドや香料の島々のことより、目の前の、水平線の向こう側に行くのが大問題であった。水平線の向こうは海水が落ち込む滝になっているとか、あるいは、滝の落下点にはバケモノが口を開けて海水を飲みつづけているとか、何があるかわからない世界であった。降雨、雷、霧、竜巻などの自然現象は、妖怪・魔物のしわざであると信じられていた。実際、探検航海中に雷鳴交じりの嵐に遭遇して逃げ戻ったチームもあった。逃げ戻った乗組員のネジを巻いて再び送り出すのもエンリケ王子の役目であった。王子が没した後の探検事業はポルトガル王室が国家事業として引継ぎ、ひたすら東洋航路(インド航路)の開拓をめざした。
② 喜望峰の発見
1488年1月、インドへの途を求めてアフリカ西岸沿いに南下していたポルトガルの探検船隊(司令官:バルトロメウ・ディアス)は、南緯29度付近で嵐に遭って13日間も漂流し、陸地(アフリカ大陸)を見失ってしまった。嵐が収まったあと、見失った陸地を求めて東に進んだ。見失う直前まで陸地は船隊の東方に見えていたのである。しばらく東に進んだが陸地を発見できない。不審に思ったディアスは針路を北に変えて進んだ。しばらく進むと、左舷前方に陸地が見えてきた。嵐に巻き込まれて陸地を見失っている間に、船隊はアフリカ大陸の南端を通り過ぎていたのである。念のためにそのあと数日は付近の地形を調査し、2月3日に岬の東にあるモッセル湾に上陸した。 この日をもってディアスは「アフリカ最南端到達の日」とした。昨年8月のリスボン出航からおよそ半年経過しており、乗組員の忍耐も限界に達して、これ以上の航海の継続は難しいと判断したディアスは岬(アグラス岬)を巡って引き返した。引き返して間もなく新たに岬を見つけ、その岬を「嵐の岬」と命名した(後にジョアン2世が喜望峰と改名)。先日、暴風に巻き込まれて10日余も陸岸を見失っていた際に、この岬に気づかないまま通過していたので嵐のイメージが強かったのであろう。
1488年12月、およそ16カ月に及ぶ航海を終えてディアス船隊はリスボンに到着、国王ジョアン2世に航海の成果を報告した。ディアスの祖父も父も、エンリケ王子に仕える船乗りであった。王子は1460年に没しており、ディアスはジョアン2世に仕えていた。彼の名は(アフリカ大陸南端の)アグラス岬および喜望峰の発見者としてポルトガルの歴史に燦然と輝いている。
(* 一般に喜望峰はアフリカ最南端と混同されることが多いが、アフリカ最南端はアグラス岬である。喜望峰はアグラス岬の北西方にあり「アフリカ南西端」になる。この岬をディアスは「嵐の岬」と名付けたが、ジョアン2世はインド航路開拓のめどがついたという意味で「希望の岬(Cape of good hope)」と改名した。“喜望峰”という漢字表記は日本人が翻訳した際に喜や峰の字を当てたから、と言われている)
ディアスのアフリカ南端到達以後、インド航路開拓をめざすポルトガルの活動はしばらく足踏みしていた。 その最中の1492年、スペインを出発して大西洋を西に向かったクリストファー・コロンブス(以下、コロンブス)の探検船隊は、アジアの一部と思われる島に到達した。到達した島は現在のバハマ諸島中のサン・サルバドス島であるが、コロンブスは到達した島をアジアの一部であると誤解した。その後周辺のいくつかの島に上陸して住民とも接触したコロンブスは、略奪した金・銀の装飾品や捕らえた住民を持ち帰ってスペイン王室に献納し、王室から約束の報酬をうけとった。このニュースに接してポルトガル王室はショックを受けた。香料群島先陣争いでスペインに先を越されたかも知れないと思ったのである。トリデシリャス条約はこのタイミングで交渉が始まった。
③ トルデシリャス条約
1492年8月、クリストファー・コロンブス(以下、コロンブス)率いるスペインの探検船隊はスペイン・パロスを出発したあと大西洋を西に向かい、アジアの一部と思われる島(後にサンサルバドス島と命名)に到達した。当時、スペインやポルトガルは交易ルートの拡張や領土拡張を意図して探検船隊を盛んに送り出していたが、その活動範囲は未だにアフリカ大陸北西部から西部ギニア湾一帯に限られており、ようやく数年前(1488年)にポルトガルのバルトロメウ・デイアスがアフリカ大陸南端を確認し、インド航路発見の希望が湧いたところであった。
ヨーロッパの地理学者や船乗りたちの間ではすでに地球球体説が支持されるようになっていたが、コロンブスの航海はそれを実証することにもなった。
地球は丸い。しかし、丸い地球のサイズがまだよくわからなかった。海や陸地の配分もよくわからない。要するに全体的な地球表面の様子がまだはっきりしなかった。地理学者もふくめて当時のヨーロッパ人はアメリカ大陸の存在も太平洋の存在も知らなかった。人々の地理的常識は自身の目に見える範囲にしかなかったのである。
コロンブスはスペインのパロスから出発して大西洋を西に進み、バハマ諸島に突き当たった。そこで彼は突き当たった場所をアジアの一部と思いこんでしまった。彼はこの航海を含めて合計4度も探検航海を行っていながら、結局はカリブ海一帯からパナマ地峡にかけての調査・掠奪にとどまり、自身が到達した島々がアジアの東端であると信じて一生を終えた。そこに南北二つの大陸が存在することさえ気がつかなかったのである。
しかし、このことをもってコロンブスを無能よばわりしてはいけない。探検航海の出発にこぎつけるまでの苦労にはじまって、ついに大西洋を横断してカリブ海の島々に突き当たった、そのこと自体はまぎれもない世界史上の偉業であった。
コロンブス船隊の帰還報告を受けて、スペイン王室はもちろん、隣国ポルトガルの王室や富裕層、船乗りたちは色めき立った。船大工の世界も急に忙しくなった。
当事、神聖ローマ帝国の教皇はスペイン出身のアレクサンドル6世であった。コロンブスの新天地発見のニュースに接して教皇は、今後、スペインとポルトガル両国間で領土獲得競争が激化することを危惧した。教皇は、紛争防止のために何らかのルールを定める必要があると考え、両国の権益区域を設定する案を提示した。見つけた獲物(領土)の取り合いにならないように、最初からそれぞれの領域(縄張り)を定めようということである。
教皇が示した案は、イベリア半島の西方、ヴェルデ岬諸島の西100レグア(約513キロメートル)を通る子午線を基線として、基線の西側(コロンブスが到達したという新天地側)をスペインの権益範囲とし、東側(アフリカ大陸側)をポルトガルの権益範囲とする」、というものであった。
ポルトガルは教皇案を不服として拒否した。二つに分けた領域のポルトガル側の取り分が小さいように思えたのである。それも具体的な根拠があるわけではなく、感覚的なものにすぎなかったが。
あらためて両国代表が協議した結果、基線の位置(縄張りの境界線)を教皇案から270レグア西にずらし、「ヴェルデ岬諸島の西方370レグア(約2、194キロメートル)を通る子午線」と修正して合意にこぎつけた。 条約名“トリデシリャス”は、両国代表が協議したスペインの町の名にちなんでいる。
この基準線は現在使用されている経度線で表すと、西経46度37分にあたる。この子午線を地球の裏側にまで延長すると、東経133度23分の子午線になる。現在の日本地図によれば、この子午線は鳥取県米子~広島県福山を通る線で、さらに南へ伸ばすと、(愛媛県)新居浜~(高知県)須崎を通り、これは四国をほぼ半分に切っている。室町時代の日本国は天皇も将軍も一般庶民も知らぬ間に二つに分けられ、中国地方の一部、四国の西半分、九州全域はポルトガルの、それ以東の近畿・東海・東日本はスペインの海外領土となるところであった。もちろん、そのようなことになるとは条約当事国であるスペイン・ポルトガル両国とも夢にも思っていない。そのような時代であった。
東経133度23分の子午線を土佐の須崎からさらに南に伸ばすと、太平洋をパラオ諸島付近、ニューギニア島西部のワイゲオ島を通る。肝心の香料群島(マルク諸島)はこの子午線の西側に位置する。つまり、正確に言えば香料群島は(トルデシリャス条約上は)ポルトガルの領域にあったのであるが、この時点で正しい世界地図を描ける者は地球上にまだ誰もいない。スペインポルトガル両国とも、香料群島は我が領域内にあると思いこんだり、もしかしたら相手の領域内かもしれないと疑ったりしていた。トリデシリャス条約とはそのような時代背景の中で生まれた条約であるということを確認しておきたい。
イベリア半島の冒険者たちはナタでスイカを割るように、寸法のよくわからない地球をふたつに割って、スペインは西回り(大西洋をアメリカ大陸の方へ向かう)、ポルトガルは東回り(大西洋をアフリカ大陸西岸沿いに南下)で、マルク諸島一番乗りを目指した。
④ インド洋制圧
コロンブスのインディアス(インド圏)到達の報せに、スペインに先を越されたと思ったポルトガル王室は腰がぬけるほど驚いた。油断していたわけでもないだろうが事業スケジュールが思うように進展しなかったのであろう。ようやく、1497年7月8日、提督・ヴァスコ・ダ・ガマ(以下・ガマ)が率いるインド洋派遣艦隊がリスボンを出発した。
満を持してエースの登場であった。ガマは順調に船脚を進め、喜望峰を迂回してアフリカ東岸のモザンビークを経由、翌年(1498年)5月20日、インド西岸のカリカットに到達した。リスボン出発以来およそ10カ月の長い航海であったが、ついに海路でリスボンとインドのカリカットが繋がったのである。インド航路開拓という偉業を成し遂げて帰国したガマは、ポルトガル王マヌエル1世に賞賛され、永世名誉インド総督に任じられた。ガマのカリカット到達以降、ポルトガルはカリカットをインド洋一帯における活動の拠点として活用し、次の作戦・マラッカ攻略へと進むことになる。
ガマのインド航路開拓を受けて、ポルトガルはインド洋に派遣する艦隊の規模を増強した。ここが勝負どころとみたのであろう。 第2回目のインド派遣艦隊は1500年3月、ペドロ・アルヴレス・カブラル(以下、カブラル)の指揮で13隻編成、第3回目は再びガマが指揮を執り、20隻編成(その中5隻はインド方面常駐の警備艦隊として)の大艦隊を送り出した。ガマはこれまで2度の艦隊派遣を省りみて、インド各地との取引に際してはこれまでのような友好親善第一の姿勢を改め、武力を前面に押し出すように考えを改めていた。戦術の大転換である。前記のとおりインド洋常駐の警備艦隊を用意し、大砲、銃器など各艦の武装も増強した。当時、カリカットやゴアをはじめインド洋各地の交易ルートはほとんどイスラム教徒の支配下にあった。イベリア半島からやってきた白人のキリスト教徒は基本的に敵対勢力である。ガマもカブラルもこれまで何度か痛い目に遭っていた。戦術の転換はこれまでの苦い経験から導き出されたものであった。
1506年、第2代インド総督アフォンソ・デ・アルプケルケ(以下、アルプケルケ)は16隻からなる艦隊を率いてリスボンを出発した。翌1506年、インド洋に進入したアルプケルケ艦隊は、インド洋西部・紅海の入り口にあるソコトラ島を、続いてペルシャ湾のホルムズ島を急襲し占領した。両島はそれぞれ紅海とペルシャ湾入り口に位置しており、地中海・東ヨーロッパ圏とアジアを結ぶ交易ルートの要衝であった。
ホルムズ島に次いてアルプケルケが狙ったのは、インド洋の東の関門マラッカ海峡であった。マラッカ海峡はマレー半島とスマトラ島に挟まれ、インド洋と東南アジア・東アジアを結ぶ関門である。海峡の中ほど、マレー半島側にあるマラッカ王国(現在のマラッカ市)は、この関門を押さえてアジア随一の交易センターとして繁栄していた。
1510年、アルプケルケはマラッカ王国に対して攻撃を仕掛けたが最初は失敗に終った。態勢を立て直して翌年(1511年)に再度攻撃してマラッカ王国を攻め陥した。このマラッカ攻略戦に、フランシスコ・セラン(以下,セラン)とマゼランがアルプケルケ艦隊の士官として参加していた。この仲良し従兄弟の運命については次号で述べる。
マラッカを陥落させたアルプケルケは時を置かずに香料生産の本丸マルク諸島に手をのばした(1511年12月)。香料群島を目指すポルトガルの挑戦はいよいよ終盤戦を迎える。
⑤ マルク到着
インド総督アプリケルケは香料獲得レースの仕上げを行うべく、3隻から成る分遣隊を編成した。司令官にアントニオ・デ・アブレウ(以下、アブレウ)を据え、副司令官としてフランシスコ・セランとシマン・アフォンソ・ビジクドの2名を指名、3人はそれぞれ1隻のキャプテンとしてマラッカからマルク地方を目指すことになった。マルクにおける最初の目的地はバンダ諸島、続いてテルナテ島に寄る計画であった。
副司令官のひとりフランシスコ・セラン(以下、セラン)には、マガリャンシス・マゼラン(以下、マゼラン)という名の仲のよい従弟がいた。二人はアプルケルケ傘下の海軍士官としてマラッカ攻略戦にも参加していたが、マルク遠征チームにマゼランは加わらずマラッカに居残って警備に当たることになった。いよいよマルク地方に向かう船隊に対して、インド総督・アルプケルケはこの作戦の基本方針を次のように示した。 ①他の船を追跡したり拿捕したりしないこと ②入港した土地では必ずその土地の首長に土産物を贈り挨拶すること ③上陸する際は2~3名の少人数で上陸すること。土地の住民と諍いを起こさないこと、④ 航海途中に立ち寄る港およびマルクの港で他国の交易船と遭遇したら決して敵対行動をとらないこと、等々。要するに、土地の住民のみならず外国船とも決してもめ事を起こすな、友好親善を前面に出せ、ということである。これまでの基本方針を裏返したのである。
インド洋に進入以来マラッカ攻略までのポルトガルの強圧的な外交は、これまでアジア圏内に形成されていた交易網を砲撃でぶち壊すことでもあった。恐れをなした諸国の商人や交易船がマラッカに近づかなくなった。交易船が近寄らない港は交易センターになり得ない。アジアの交易センターであるマラッカはその機能を失いかけていた。遅まきながらそのことに気づいたポルトガル勢は外交方針を変更した。
1511年12月某日、アブレウ船隊はマラッカを出発した。ポルトガルの船乗りたちにとってマラッカからマルク諸島までおよそ4千キロの航路は初めての体験であるが冒険航海というわけでもなかった。この海路は当時すでにマルク地方とマラッカを結ぶ商業航路として出来上がっていた。当然、航路に慣れた船乗りも多く、現実にアブレウ船隊もマラッカ出発に際して水先案内人数人を調達し乗り込ませていた。“楽勝”と思えたマルク遠征であったが、何故か、セランの乗船は不運が続く。
当初の航海計画では、船隊は最初にバンダ諸島に寄ってナツメグを集荷し、その後テルナテ島に寄ってチョウジを集荷する予定であった。バンダとテルナテを香料交易の集荷拠点に仕立てる計画であったと思われる。ところが実際にはバンダ諸島に到着する前に船隊はアンボン島に立ち寄った。これは単純に航海技術上の問題でそのようなったと思われるが、これでいろいろと予定外の事態が生じた。まず最初に、アンボン島でセランの乗船が座礁事故を起こし、船体を放棄した。セラン以下乗組員は司令官アブレウの乗船に収容されバンダ島に到着した。(その後、バンダ島でアブレウは地元の商人からジャンク1隻を購入し、セランのチームはそれに乗り移った)。次に、アンボン島からバンダへ向かう予定が座礁事故のために大幅に遅れて(バンダ島行きの)季節風の時期を逃がしてしまった。そのためにセラム島の南端で約3か月も風待ちを余儀なくされた。つまりバンダ諸島到着が大幅に遅れたのである。
バンダ島での香料集荷は順調に進んだ。バンダ島特産のナツメグとアンボン島から運ばれてきた丁子を船腹いっぱい仕入れた船隊は、すでにここまで日数もかかり過ぎていることからテルナテ島行きを中止してバンダから直接マラッカに戻ることになった。
バンダ島を出発したアブレウ船隊は翌日の夜明け前から強烈な風雨に見舞われて、3隻が互いに僚船を見失ってしまった。嵐の中でセランの乗船はまたしても座礁事故をおこし、大破してしまった。現場はプロープニュー(亀島)と呼ばれる無人島で、乗組員は辛うじて島に上陸することができた。(死傷者も出た模様であるが詳細は不明)
亀島には食料も水もなく遭難者たちは途方に暮れたが、次の日に素性不明のジャンクが島に寄ってきた。生田滋著「大航海時代とモルッカ諸島」(中公新書)ではこの船を“海賊船”としているが、本当のところはどうであろうか。東南アジアの海は現代でも漁船・貨物船・追剥ぎ(海賊)船、区別のつかない船がうろうろしているが、これは昔からの伝統文化かもしれない。状況に応じて適当に対応するということであろう。
セラン一行は“海賊”の首領と談判して、最寄りの島アンボン島まで運んでもらうことになった。亀島からアンボン島西端まで、北方向におよそ200キロメートルの距離があるる。(ちなみに、彼らが出発してきたバンダ諸島は東北東におよそ250キロメートル。セラン一行が行き先をバンダ島ではなくアンボン島を選んだのは、遭難現場からの距離的な問題だけではなく、遭難を奇禍として本来は彼らが最終目的地としていたテルナテ島へ近づくために、とりあえずアンボン島へと考えたのであろう。
セラン一行は、アンボン島西北部にある村(現在のアシルル村)に到着した。この時点でポルトガル人は6,7名であったらしい。マラッカで雇い入れた水先案内人や奴隷が何人残っていたかはっきりしない。
アシルル村で彼らは地元民の狩猟を手伝い、ときには近隣集落との戦いの助太刀をしながら、テルナテからの迎えを待った。マルク海は波の静かな内海で、海を渡るには手漕ぎ又は帆走の小船があれば十分可能である。連絡・通信は口伝または手紙に頼った。アンボン島アシルルからテルナテ島までは島伝いに海上をおよそ500Km、移動手段は船だけである。
テルナテのボレイフェ王はセラン一行がアンボン島アシルルに到着したという情報をいくつかのルートで手に入れていた。また、交易都市マラッカ王国がポルトガル海軍の攻撃を受けて陥落したこと、その影響で香料の流通が混乱していることを知っていた。その混乱を引き起こした張本人ポルトガルの1部隊がアンボン島に到着したこと、そして彼らがテルナテ訪問を希望していることをボレイフェ王は把握し、迅速に反応した。ボレイフェ王はさっそく、セラン一行迎え入れのための船団を派遣した。日付ははっきりしないが1512年末ごろのできごととされている。
言うまでもなく21世紀の現在、マルク諸島はインドネシア共和国という1個の政体の中におさまっている。現在の行政区画で言えばバンダ諸島はマルク州の南端に当たり、アンボン島アンボン市はマルク州の州都。テルナテ島は北マルク州の州都になる。現在の州区画では2個に分かれているが16世紀ボレイフェ王たちの時代にはバンダからテルナテまで一括りにしてマルク地方とよばれていた。政治的にはマルク全体を支配する政体はなくて、島々の首長が王様として君臨していた。セラム島やバチャン島など比較的面積の大きい島ではそれなりに複数の首長が存在しラジャ(王)と名乗っていた。その中でもテルナテの首長ボレイフェはスルタンの称号でよばれていた。
セラン一行はテルナテ島で歓待を受け、ポルトガル王国の商務駐在員として香料の集荷を進めるかたわら、テルナテの王宮衛兵としての役割りも請け負った。セランは衛兵隊長でありボレイフェ王の顧問として相談相手にもなった。テルナテ島はマルク地方で最も重要な島であり、マラッカを経由してヨーロッパまで続く香料交易ルートの生産地ターミナルである。セランがテルナテ王ボレイフェの心をがっちり掴んだことによって、香料貿易で国を富すというポルトガル王国の長年の夢は正夢となった。
此の頃、セランはマラッカに勤務中のマゼランあて手紙を書いている。マゼランは翌年(1513年)1月にポルトガル本国に帰っているので、手紙そのものは現在もマラッカのミュージアムに残されているらしい。手紙には状況説明のあと、「テルナテはよい場所だ。空気がよく食べ物も豊富でおいしい。あなたもここに来て私の周りにある喜びををいっしょに満喫しようではないか」と記されているとのことである。
二人が生きて再会することはなかったが、その魂魄は9年後(2021年)にテルナテで対面しているかもしれない。次号ではその後のマゼランの動きを軸に、スペイン船隊のマルク到達までの動きを追ってみたい。(第2部 完)
Copyright (c) Japan Sulawesi Net, All Rights Reserved. |