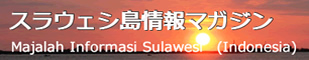 総目次 総目次 |
大航海時代とマルク諸島(3)
北スラウェシ日本人会
長崎節夫
① フェルディナンド・マゼラン(マガリャンシス・マゼラン)
前号で、1511年のポルトガル艦隊によるマラッカ攻略戦にフランシスコ・セランとマゼランが参加していたと述べた。マラッカを陥したあと、セランはマルク遠征隊3隻のうちの1隻のキャプテン(指揮官・船長)として出発、マゼランはマラッカに残り、翌年(1413)ポルトガル本国に帰った。
マラッカを出発したマルク遠征隊は,ジャワ島、アンボン島を経由してバンダ諸島に到着し、香料(ナツメグ、メース、クローブ)の取引を成功させた。香料を積み込んだ遠征隊はマラッカに帰る途中で嵐に遭遇した。2隻は難をのがれてマラッカに到着したが、セランの乗船は座礁事故を起こし、乗組員は遭難現場の無人島・プロープニュー(亀島)に上陸した。その後セラン他数名の乗組員は現地住民の船に運んでもらってアンボン島北西部にあるヌサテラ村(現在のアシルル村)に上陸した。ヌサテラを拠点にして現地住民の争いごとの助太刀にでたりしながらテルナテ島行きを画策した。セランの目論見通りテルナテから迎えの船団がやってきて、セラン一行はヌサテラから北方およそ500kmにあるテルナテ島に運ばれた。
テルナテ島は現在もそうであるが、セラン隊がたどり着いた1512年当時もマルク諸島中最大のクローブ(丁子)生産地で、香料諸島の「本丸」と言ってよい。ポルトガル勢は先のバンダ諸島到着と併せて、これでヨーロッパ勢としてははじめて香料諸島(マルク諸島)達したことになる。
この時点で、スペインの探検家たちは未だ、コロンブスが発見したと言う新天地(アメリカ大陸)の向こう側(太平洋側)へ抜けることが出来ていない。新天地の開拓(現地住民からすれば侵略・略奪)に熱中して、香料諸島のことは意識から飛んでいたのかも知れない。
テルナテに到着したセランはポルトガル代表として香料取引きを取り仕切りながら、ボレイフェ王と親密な関係を築き上げていた。ポルトガル隊は少人数ながらテルナテ王宮の護衛としての役割りも請け負ったので、セランはテルナテ駐在の商務員であり、王宮の衛兵隊長でもあった。彼は同年(1512年)末にマラッカ滞在中のマゼランあて近況報告の手紙を書き送っている。
一方のマゼランは1513年1月にマラッカを去りインドのコチンを経由してポルトガル本国に帰った。帰国後はモロッコ(北西アフリカ)遠征に参加して戦功を立てたが自身も重傷を負った。モロッコから本国に戻った後、彼自身が探検船隊を率いて西回りでマルク諸島に向かいたいということをマヌエル王に具申したが拒否された。
マゼランの説明によると、ポルトガル本国から大西洋を横断して新天地(アメリカ大陸)のどこかにある海峡を通り抜けたら香料諸島はすぐそこにある。ポルトガルが現在利用している(喜望峰を迂回する)東回り航路のおよそ三分の一の航程で済むので、時間・コストがそのぶんだけ節約されて有利である、ということであった。
マゼランの地理的な認識はコロンブスの時代からほとんど変わっていないが、それが当時のヨーロッパ社会の常識であった。一流の地理学者が作成した世界地図でも、アメリカ大陸はまだ存在せず太平洋という大海の存在すら認識されていなかった。要するに地球の大きさも陸地や海洋の分布もまだよくわかっていない時代のことで、仕方のないことではある。
マヌエル王がマゼランの要望を拒否したことについては、王とマゼランとの間に感情的なしこりががあったという説もある。また、隣国スペインとの間に締結されたトリデシリャス条約のたてまえ上、西回りの航路を採用することはスペインの権益を冒すことにつながりかねないのでポルトガル王室としてはマゼランの西回り案を受け入れるわけにはいかなかったとも考えられる。
② マゼラン船隊の出発
ポルトガル王室に断られたマゼランは隣国スペインの王室と折衝することになった。スペイン王室との折衝にあたってはドイツのフガー商会代理人・クリストバル・デ・アロや、スペイン王室の実力者であるホアン・ロドリゲス・デ・フォンセカなどがからんいる。この頃、マゼランのまわりにはマルク遠征を推進するプロジェクトチームができあがっていたかのようである。彼らはマルクへの船隊派遣を個人的な投機としてとらえており、派遣実現のために彼らなりに努力していた。
結果を言えば、船隊派遣の件は国王の承諾を得ることが出来て、マゼランを総司令官とするマルク遠征隊を派遣することが決まった。ポルトガル人マゼランがスペインナショナルチームの総監督になったのである。
遠征艦隊派遣の話はすんなり決まったが、そのあとの準備は“すんなり”とはいかなかった。最大の問題は遠征資金の調達で、最終的に費用の大半はアロを通してフッガー商会が工面した。
この時期、ポルトガル勢力はすでにマルク諸島に到達していて、香料はじめ東洋の産品をリスボンに運び込んでヨーロッパ市場に流通させていた。これまでのベネチアに代わってリスボンが香料貿易のセンターになり、ポルトガルの経済力は急伸した。隣国スペインとしては指をくわえて見ているわけにはいかない。
ただ、ポルトガルに比べてスペインの場合は造船技術をはじめ海洋技術のレベルが一段低いことが問題であった。例えば探検船乗組員の編成にあたってもスペイン人船員だけでは必要な人材をまかなうことができないため、熟練したポルトガル人船員を補充せざるをえなかった。これは航海の実施にあたって、航海の初期からチームワーク上の問題を引き起こすことにつながった。調達した5隻の探検船すべてが中古船であったこと、また、航海用食料の積み込みに際して領収のミスに気づかず食料不足の状態で出発してしまったことも、運航業務の不慣れから起きた失敗として挙げられるであろう。
あれやこれやで寄せ集めチームの出発準備は遅々として進まず、しびれを切らした国王カール5世は強制的に出航日を決めた。1519年8月10日、マゼラン船隊は国王の命令どおりセビリアを出発してサンルーカルに寄り、そこで準備を完了させて9月10日サンルーカルを出航した。探検船5隻、参加人員は司令官マゼラン以下総数265名(そのうちポルトガル人は37名)であった。
③ マゼラン海峡発見
前号でも述べた通り、現代に伝わっているマゼランの「世界一周」説は誤りである。彼は世界一周の実行どころか世界一周を企画したことすらなかった。彼の航海計画は西回り航路でアジアの香料諸島まで赴き、船腹いっぱい香料を詰め込んでスペインに持ち帰ることであった。地球を1周する航海を行うことは1ミリも考えていなかった。実際には、マゼランはほぼ地球を半周して力尽きたことになるが、それでも彼は この航海で世界史に残る殊勲を2個もあげ、「マゼラン」の名を世界史に刻んだ。
最初の殊勲はマゼラン海峡の通航に成功したことである(“マゼラン海峡”は通航後の命名)。コロンブスの新天地到達以降、スペインの航海者たちの最大のテーマは、大西洋から“むこう側に”通り抜ける航路を見つけることであった。なにしろ、コロンブスが見つけたと言う“新天地”のすぐ向こう側に香料諸島があると考えられていたのである。コロンブス自身も都合4度にわたって探検を繰り返し、“向こう側へ抜ける道(=海峡)”探しに躍起になったがうまくいかなかった。
1520年10月21日、南米大陸の南端付近でマゼラン船隊が進入した水路は、どうやら向こう側に抜ける海峡であるらしいと予感された。船隊は迷路のような水路を慎重に進み、11月28日、船隊はついに向こう側の大海に出た。(この海峡はのちにマゼラン海峡と名づけられ、大海は太平洋と名付けられた)。
1520年11月28日、海峡を通り抜けたマゼランはどのような感慨を抱いたであろうか。前方に広がる大海を眺めて、ここまでの苦労も吹き飛んだ思いでいたのだろうか。当然ながら、船隊の誰一人として目の前に広がる海の実際の広さに気づいた者はいない。
この時点でマゼランの船隊は3隻になっている。スペイン出発5隻のうち1隻はパタゴニア付近で難破、1隻は海峡にさしかかってから脱走しスペインに逃げ戻った。
④ 太平洋横断とマゼランの戦死
海峡を抜け出た船隊はしばらくの間、南米大陸西岸(チリ沿岸)伝いに北上した。マゼランの予備知識によると、目の前に広がる海は大洋ではなく大きな“湾”であるはずであった。ここ(海峡を通りぬけた場所)は湾の入り口で、もう少し進めば湾奥に行き当たって、左手にはアジアの島々が現れるに違いない。ところが行けども行けども海岸線は北方に伸びていて、湾奥に突き当たる様子はない。これはおかしいと感じたマゼランは現在のパルパライソの手前あたりで北西に針路を転じた。
南米大陸は後方に消え去って、前方はどこまで続くかわからない海が広がっている。雲煙万里という言葉はスペイン語にもあるだろうか。すでに船隊の食料不足は深刻な状況になっており、乗組員は栄養不足のために病気(特に壊血病)で次々と倒れ、死者もでるようになった。
マゼラン海峡を抜けて太平洋に入ってから3か月経過し、はじめて人間の住む島に行き当たった。船隊は水・食料の補給を図ったが、逆に現地住民による略奪行為に遇ってその島を逃げ出した。その島をマゼランは「泥棒島」と命名した。これは現在のグアム島らしい。泥棒島を離れてさらに西に進むこと2週間、1521年3月16日、フィリピン群島・サマール島南端に連なる小島に到着した(フィリピン群島も後の命名)。船隊としては全く想定外の困難な航海で多くの犠牲も出たが、この航海によって新大陸とアジアの間に広がる大洋(太平洋)の存在が明らかになった。マゼランはじめ船隊乗組員の誰一人として意図しなかったことであったが、彼らの3か月にわたる航海によって地球上最も広い海洋の存在が証明されたのである。これはまぎれもない世界史上の大殊勲であった。
彼らが到達した島々は目指す香料諸島ではなかったが、かなり近くまで来たことは皮膚感覚として十分に感じ取られた。しかし、マゼランは急がなかった。急がなかったというより、彼にとってはキリスト教の布教も香料諸島到着と同等の重要任務であったに違いない。とりわけセブ島ではセブ王の好意を得て現地住民へのキリスト教布教に熱をあげた。セブの中心地(現在のセブ市)から漸次周辺集落にも布教の手を広げ、セブ島対岸のマクタンにも乗り込んだが、マクタンの首長ラプラプはマゼランの強引な不況活動に反感を持った。
現在はセブ島(セブ市)と陸続きになってセブ国際空港になっている場所がかつてのマクタン島である。狭い水道を挟んでセブとマクタン、二つの部族が日常的に対立しているわけではなくても微妙なバランスで存在している。そのような場所に飛び込んだマゼラン船隊はうまく利用された可能性がある。1521年4月27日、セブ王の勧めもあってマクタン島に乗り込んだマゼランは首長ラプラプが指揮するマクタン勢に打ち取られてしまった。マスケット銃(火縄銃の1種)と長刀(ナタ)で武装したスペイン勢60名が乗り込んだマクタン島の海岸には1300余名のマクタンの兵士が待ち構えていて白兵戦になった。多勢に無勢、どうにもならなかったらしい。スペイン船隊側では乗り込む前に兵力の差を案じてマゼランの出陣を止めさせようとする動きもあったらしいが、マゼランはなぜか自信満々で、負けるわけがないと言い残して乗り込んだらしい。
スペインを出発してからここまでおよそ2年と3カ月、マゼランの長い旅はフィリピン群島のマクタン島であっけなく終わった。
マクタン島の戦いで8名の仲間を失って落ち込んでいる船隊に、セブ王から激励の宴を催すからということで招待があった。船隊の幹部級の者も含めて約40名が参加したが、実はセブ王が仕組んだだまし討ちで、40人近くが殺され、生き残りの数人は捕らえられた。昨日の友は今日の敵ということか。
マゼランがフィリピン(マクタン島)で戦死する2か月ほど前に、ポルトガル代表としてテルナテ島を拠点に活動していたセランが毒殺された。毒を盛ったのはティドレ島のアル・マンスール王であったらしい。ティドレ島はテルナテ島に隣接する島で、首長どうしは縁戚でもあって親しく行き来していた(テルナテ王の正室はティドレ王アル・マンスールの娘)。それでも、地域の主導権を巡っては油断できない関係でもあった。セランは丁子買取りのためにティドレ島を訪れていたが、アル・マンスール王にすすめられて毒を仕込んだキンマを口に入れてしまった。
セランの死後10日目にはテルナテのボレイフェ王も側室に毒を盛られ死亡した。ボレイフェ王の側室はバチャン王の娘であった。バチャン王アラウッディーンはテルナテ王ボレイフェの腹違いの弟であり、二人は仲がよかった。マルク諸島の有力首長たちは互いに血縁であったり、婚姻などの手段でつながって表向きは親密に接しているが、状況によっては何時でも敵に回るような、油断ならない関係であったと言える。
一方、マクタン島とセブ島で総大将マゼランはじめ多くの仲間を失ったスペイン船隊はセブ島の南のボホール島に立ち寄り、航海継続の準備を行った。そこで老朽化によって浸水がはなはだしいコンセプシオン号を焼却処分し、乗組員の再編成をおこなった。残るのはビクトリア号、トリニダード号の2隻となった。(ビクトリア号は最終的にインド洋経由でスペインに帰り着いて史上初の世界一周航海を達成することになる)
さて、目指すマルクは何処ぞ。目的地マルク諸島は近いという感覚はあるが、それが西か東か、南か北かさっぱりわからない。そのあたりの住民に尋ねても要領を得ない。ただ、一人の漁師が「この方向に行けばブルネイという大きな港町がある。そこで聞けばマルクの場所が分かるかも」と西を指して答えた。船隊はさっそくミンダナオ海峡を西へ向かい、スルー海を通り抜け、バラバック水道から南シナ海に入った。南シナ海でもブルネイを捜して右往左往し、ようやくボルネオ島西北岸にあるブルネイ港を見つけた。
当時、ブルネイはアジア交易圏の中でも重要な港町であった。マラッカを中心にして東西南北に交易海路が伸びているが、カンボジア、ルソン、台湾、琉球等、北方面の貿易船はブルネイを中継港とするのが常であった。
スペイン船隊はブルネイ湾でジャンク(交易船)4隻を襲って積み荷を掠奪し、乗組員を捕らえて捕虜とした。このあたりからスペイン船隊は海賊船に変身した。船長もこれまでポルトガル人が務めていたのを、トリニダード号はゴンサロ・デ・エスピノサ、ヴィクトリア号はファン・セバスチャン・デ・エルカーノ(以下、エルカーノ)と、両船ともスペイン人船長に代わった。
捕らえた捕虜の尋問などによってマルク諸島のおおよその方向を察知した船隊は、針路を東に変えてミンダナオ島の南岸沖(セレベス海)に進入した。ミンダナオ島の南岸沿いに東進した。この間にも洋上のカヌー(漁船)を襲って漁師を捕らえ、水先案内を命じた。
サランガニ島に達して南に変針。サンギル諸島沿いに南下して前方にミナハサ半島の山々(クラバット山など)を視認すると東北東に変針。いよいよゴール前の直線コースに入った。
11月6日、東方の水平線上に山頂を発見した。捕らえた捕虜(案内人)から「あれがテルナテだ」と聞いた船隊員一同は歓声を上げ礼砲を撃ち放した。
11月8日日没3時間前、船隊はテルナテ島南隣のティドレ島に到着した。スペイン側は、すでに8年前(1512年)にポルトガルのセラン隊がテルナテに到着して香料取り引きを開始していることを知っていた。そのためテルナテ島を避けてティドレ島に入港したわけであるが、それは正解であった。
ティドレ王アル・マンスールはスペイン船隊を待ちかねていたかのように歓迎した。船隊はマンスール王への土産として南シナ海やセレベス海での海賊行為によって掠取した品々(布地等交易用商品)を贈呈した。ここでスペインの隊員達はテルナテに先着していたセランの死についても知らされた。スペイン船隊の行動を詳細に書き残したアントニオ・ヴィガフェッタの記録によると、セランの死は1521年3月のはじめということになっている。もしそのとおりであるならばセランはマゼラン戦死のほぼ1か月前に没したことになる。
スペイン船隊のティドレ島到着は1521年11月8日。セラン(ポルトガル隊)のテルナテ島到着は1512年(月日不明)で、およそ9年の時間差がある。ポルトガル勢は当然ながら香料交易において9年分の実績を積み、有利な立場を築いていた。その後、ポルトガル勢とスペイン勢、いろいろとつばぜり合いもあったが、スペインはフィリピンの経営に力をそそぐようになり、徐々にマルク諸島から手を引いた。
⑤ 終わりに
本稿で扱った大航海というのは、時間的にはポルトガルのエンリケ王子が生まれた14世紀末から、ポルトガル・スペインのマルク諸島遠征隊がテルナテ島およびティドレ島に到着する1521年5月ごろまでの範囲で、内容的にはイベリア半島両国(ポルトガルとスペイン)によるマルク諸島一番乗り競争を軸にして説明を試みた。というわけで、最後まで残って世界一周を達成したヴィクトリア号のマルク以降の動きについてはあえて触れなかった。取扱い範囲をしぼったつもりであるが、ページ数だけが増えて内容はレンコンの輪切りみたいになってしまった。
Copyright (c) Japan Sulawesi Net, All Rights Reserved. |