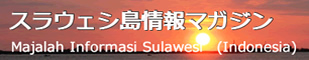 総目次 総目次 |
日系人メモ・・大岩勇の遺産
Warisan ISAMU OHIWA di Bitung
長崎 節夫 Nagasaki Setsuo
Nelayan Jepang membawa cara penangkapan ikan Cakaran ke desa Bitung melalui Palau pada sekitar tahun 1930. Pada waktu itu Bitung hanyalah sebuah desa kecil. Mr.Ohiwa Isamu (1902-1945), pengusaha asal Aichi-ken, Jepang, memainkan peran kunci dalam pengembangan Bitung sebagai kota industri perikanan terkemuka di Indonesia.
北スラウェシ州の海の玄関口としてめざましい発展をみせるビトゥン。ビトゥン発展の基盤になっているのは「港」である。ビトゥン港は、スラウェシ島の北東、ミナハサ半島のほぼ先端にある。州都メナドの近郊に位置する立地の良さに加え、大型船舶の出入りにも十分な水深があり、なおかつ外洋からの風波を遮断する地形の良さがある。いわゆる「天然の良港」である。
インドネシア中央政府としてもビトゥン港を東部インドネシアの主要港として位置づけており、港湾整備を進め、水産加工、椰子油加工、ドックなど、港湾型工業地帯の造成に力をいれている。
工場の新・増設、道路改修、住宅建設と、町全体が活気に満ち人口も急速にふくれあがりつつあるビトゥンであるが、昭和の初めごろ(1930年前後)この地を訪れた漁業調査船(鹿児島県・民間)のスタッフは「人家もまばらな寒村」と報告している。
この寒村にかつお釣り漁業を持ち込んで、のちのビトゥン市の発展につなげたのは、昭和初期の日本人漁民たちで、その中でも中心的なな役割をはたしたのが愛知県出身の大岩勇という男であった。

上の写真:昭和16年2月11日(紀元節)、日本領事館の前庭にて
前列着席の大人の左から4番目が大岩勇、その右が在メナド領事
大岩勇(いさむ)は明治35年(1902)愛知県知多郡豊浜町の中川(安吉)家・三男(7人兄弟の3番目)として生まれた。幼少時に、中川家と親しい大岩家に養子として迎えられ大岩姓となるが、実質的には中川家(実家)で育った。
中川家は愛知県豊浜の資産家で、勇の祖父・豊吉の代に横浜(新子安)で造船業を興した。造船所は横浜・新子安の運河沿いにあり、小型の木造漁船や貨物運搬用の艀(はしけ)などを建造した。造船業と関連して製材業も営み、さらに船舶用エンジンの製作や修理のための鉄工所も経営していた。
新子安の自社造船所で船大工としての腕を磨いた勇は、夢を抱いてミクロネシアのパラオへ渡る。(昭和4年ごろと推定される)
パラオ群島を含むミクロネシア一帯は、第一次大戦(大正4年・1915)のあと、日本の委任統治領となっていた(それ以前はドイツ領)。昭和初期の日本は、金融恐慌にはじまって世界的な経済恐慌とつづき、不況のどん底にある。不況打開の途として、新たに日本の委任統治領となったミクロネシア(南洋群島)に目が向けられ、主に農業・漁業の分野で多くの日本人が進出したのである。
南洋進出の波は、委任統治領であるミクロネシア諸島の範囲内にとどまらず、西欧諸国の植民地であるフィリピン、シンガポール、ボルネオ島、ジャワ島、そしてセレベス島にまでおよんだ。
当時のセレベス島は蘭印(オランダ領東印度)とよばれる植民地(統括する政庁はバタビア=現在のジャカルタにあり)で、北セレベス地元の産品といえば、ヤシ油、香辛料、コーヒーなどの農産物であった。そのセレベス島に、すでに明治の末期ごろから小規模ながら日本人商人や漁民(沖縄の追い込み網漁業)などが進出していた。
大岩勇がパラオを経由して北セレベスに入ったのは昭和4年(1929)と推定されるが、その15年前、大正3年(1914)にヨーロッパで第一次世界大戦が勃発し、日本は日英同盟の手前もあってこの大戦にイギリス、フランスなどの連合国として参加した。戦争に参加したといっても主戦場はヨーロッパであり、日本はそれほどの代償をはらうこともなく戦勝国の一員となってしまった。その果実として、それまではドイツ領土であった中部太平洋ミクロネシアの島々が、日本の領土(委任統治領)となって転がり込んできた。
広大な海域に点在するミクロネシア諸島(日本では南洋群島、あるいは内南洋とも称した)の支配者となった日本は、パラオ群島・コロールに南洋庁を置いて南洋群島開発を進めることになる。
政策的に企業、労働者の南洋進出を奨励し、開発の大動脈として、日本本土とパラオを結ぶ航路も開設した。別名「命令航路」ともよばれるこの国策航路は、神戸・横浜を起点に南のターミナル港パラオへ、パラオからさらに枝別れして東西に伸びていた。東はトラック諸島(現チューク諸島)、ポナペ(現ポンペイ)、ヤルート方面へ、西は日本の領域をこえてミンダナオ島南東部のダバオ(米領)、北セレベスのメナド(蘭領)まで達した。この航路に日本郵船の大型貨客船が就航していた。この時代の北セレベスは、パラオを経由して神戸・横浜とつながっていたのである。
大岩勇も、鰹釣り漁師たちも、さらには鰹節造りの職人、船大工、雑貨商、薬売りの行商人、写真屋、歯医者、衣料品の商人、商社員、領事館員その他、多岐にわたる職種の人々がこの航路によって日本と北セレベスを行き来したのである。
手元に昭和13年(1927)8月時点のメナド在留邦人名簿というのがある。名簿の元は多分、当時の在メナド日本国領事館の記録であろう。
この名簿によると、在留邦人総数は196名。そのうち漁業関係者は127名で総数のほぼ65%におよぶ。127名の内訳は、大岩漁業(造船部を含んで)73名、日蘭漁業36名、ピジャック組合18名である。(日蘭漁業とピジャック組合はこのあと昭和14、15年に大岩漁業に吸収合併された)。大岩漁業はすでにこの時点で北セレベスの日系企業のなかで存在感を示している。
事業を拡大していく過程で、勇は現地人乗組員の雇用も進めた。この現地住民の雇用が結果的には技術の移転という効果を生んで、現在の「カツオの町ビトゥン」の創成につながるのである。
昭和戦前期の日本人による南洋かつお釣り漁業(かつお節加工業を含む)は、日米開戦直前の昭和15年でピークをむかえるが、この時点で大きく次の3社に集約されていた。
日本の委任統治領、いわゆる内南洋(現在のミクロネシア連邦およびパラオ共和国)のかつお釣り漁業をまとめた南洋水産(南洋興発の子会社)、イギリス領北ボルネオ(現在のマレーシア)のシアミル島を基点に操業したボルネオ水産、そして、オランダ領北セレベス・ビトゥンの大岩漁業である。
順調に業績を伸ばす勇の事業とは裏腹に、日本をとりまく国際環境は徐々に悪化していく。昭和6年の満州事変に端を発して昭和12年の支那事変勃発、昭和15年日独伊三国同盟の締結と続き、アメリカ、イギリスとの関係が悪化していった。フランス、オランダも南進政策を進める日本に対して警戒心を強めた。特にオランダはある時期から、日本の狙いが石油ゴムなど、オランダ植民地の資源にあることを察して警戒のレベルをあげた。北セレベスの日系企業のなかでも機動力のあるかつお釣り漁船を運用していて従業員(乗組員)も多い大岩漁業は、「要注意企業」としてオランダ当局の監視対象になったであろうことは想像に難くない。
昭和6年(1931)にメナドで大岩勇と現地人女性の長男として生まれた大岩富は、10歳になった昭和16年9月、父・勇に伴われ、はじめて日本にわたった。日米開戦3か月前である。現地人である母親と幼い弟妹はメナドに残った。富の日本行きについては表向き日本の教育を受けさせるということであったが、これは明らかに開戦の危険を察知しての緊急避難ということであろう。
大岩親子はメナドから大型の貨客船でパラオを経由し神戸に到着した。大岩親子の他にも北セレベスからの引揚者が何人かいた。大岩漁業事務職員で、後に東京・世田谷区の自宅で富を預かることになる青山辰美も同じ船で帰国した。結果的にはこの船便がメナド発の(開戦前の)最後の引揚船になった。
また、日時ははっきりしないが大岩漁業従業員の一部は日米開戦の直前に鰹釣り漁船でパラオに避難した。勇の末弟・中川大八郎もパラオ避難組の一人である。しかし、全従業員が退避したわけではなく、一部はビトゥンに居残り、操業を継続していた。
12月8日、開戦と同時に大岩漁業関係者をはじめ、北セレベス在住日本人は全員オランダ官憲によって拘束され、捕虜としてオーストラリアに移送、抑留された。鰹節工場は、オランダ官憲の指示によって火を放たれ、灰塵に帰した。(複数の放火実行犯が後に日本海軍の警務隊に逮捕された。その中には鰹釣り漁船の現地人乗組員もいた。)
日米開戦によって舞台は暗転したが、1か月後にまた一転する。12月8日の開戦からほぼ1カ月あとの昭和17年1月11日、帝国海軍特別陸戦隊がトンダノ湖畔・ランゴワンのオランダ軍飛行場を空から強襲した(落下傘降下)。同時に別動陸戦隊部隊がケマ海岸とメナド湾岸に上陸、オランダ軍を排除して北セレベスは日本軍の占領するところとなった。戦況の落ち着きを待って、パラオに避難していた従業員や漁船がビトゥンにもどり、工場も再建して操業再開となった。前記、青山辰美も小学生の大岩富を東京・世田谷の留守家族に託してビトゥンに戻った。漁業基地で(飲料)水質もよいビトゥン港は日本軍の兵站基地として重視され、国策会社南洋貿易の資本参入もあって、ビトゥンの鰹釣り漁業は以前にもまして活発な操業を行うようになった。(国策会社南洋貿易が大岩漁業を吸収するかたちで「東インド水産会社」を設立)
東インド水産会社での大岩勇の肩書は専務取締役となるが、実質的な経営責任者であった。勇が、軍の協力も得て日本本土で冷凍運搬漁船を調達したのは戦局も押し詰まった昭和20年初春のことであった。
昭和20年5月、富の学童疎開先である長野県和田村に父・勇が訪ねてきた。しばしの面会のあと、親子で駅まで歩いた。これがこの世でのお別れであるとは想像もしなかったが、いま思えば父のしぐさに別れを予期しているようなものがあった、と富の述懐である。
勇は息子と別れて旬日のあと、冷凍運搬漁船・神奈川丸でビトゥンへと向かうことになるが、目的地まで到達はできなかった。 昭和20年5月20日、神奈川丸は朝鮮半島沖にて米軍機によって撃沈された。付近沿岸の住民が乗組員の一人を救助したが瀕死の重症で、間もなく息を引き取った。この日が大岩勇の命日となる。享年43歳。
話はさかのぼるが、大岩勇が北セレベスにやってくる少し前の昭和2年、鹿児島県人・原耕(はら こう)が率いる漁業調査船団(かつお釣り漁船、2隻)が台湾、フィリピンを経由してビトゥンにやってきた。同行した鹿児島県水産試験場の技師が記録を残しているが、当時、ビトゥンは人家もまばらな寒村であったという。原耕の船団は、ビトゥンからさらにアンボン、テルナテ方面まで調査操業を行い、マルク海一帯がかつお漁場として有望であることを確認した。しかし、これから本格的な操業というところで団長の原耕がマラリアに罹りアンボンで客死、計画は頓挫した。
そのあとで入れ替わるようにやって来たのが鹿児島や沖縄の鰹釣り漁業者、造船事業を目論む船大工の大岩勇などで、結果として彼等がビトゥンにかつお産業を興すことになる。
昭和20年8月の敗戦によって日本人による鰹釣り漁業の事業は消滅するが、その後、現地住民や日本の関係者の尽力によってビトゥン市の基幹産業として復活した。ビトゥン港そのものもメナド市の外港として日本のODAなどで整備がすすめられ、かつての「寒村」は、今や東部インドネシアのハブ港として賑わいをみせている。現在、ビトゥン市街地の入り口や市庁舎前庭の躍動するカツオのモニュメントが示すとおり、カツオはビトゥン市のシンボルになっている。そのビトゥンの、カツオによる町興しを始めたのは昭和初期の日本人漁師たちで、その中心的な役割を果たしたのが大岩勇であった。
勇の図南鵬翼の夢は太平洋戦争で吹きとばされたが、蒔いた種は戦後(インドネシア独立後)に芽をふいて、港町ビトゥンの発展につながったのである。大岩勇もって瞑すべし。