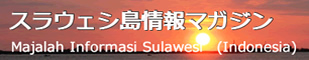 総目次 総目次 |
セレベス新聞時代を顧みて(追録)
Retrospeksi masa redaksi "Harian Pewarta Selebes"
di Makassar selama 1943-45 (Penambahan)
黒崎 久 Kurosaki Hisashi
マナイ・ソフィアンとの再会

わたしが図書編集部副部長の職にあったころ、或る朝、出社したところ、外人から電話だというので受話器を耳にしてみたら、なんとプワルタ・セレベスで一緒だったマナイ・ソフィアン氏ではないか。彼は国連大使から転任の途上東京に立ちより、帝国ホテルに宿泊し前々日かにわたしに電話をくれたのだが、電話
交換手に外国語が通じなかったのかして、たぶん黒崎は朝日新聞にでも移ったのではないかと思い、朝日新聞にも電話したところ該当者がいないことがわかった。それでも諦めきれず、もう一度毎日新聞に電話してみたところ、英文毎日に黒沢という記者がいて、その方に電話がつながった。運よく黒沢氏は翻訳出版の件でわたしのことを知っておられたので、わたしの方に電話を回してくれたというしだいである。そ
れじゃというので、わたしはセレベス新聞に出向した経験のある人たちにその旨を告げ、二度帝国ホテル
に赴き、十五年ぶりにマナイ・ソフィアン氏との再会を喜び合った。わたしはAA会議の折に会っていたから
五年ぶりであった。
セレベス新聞の初代社長であった大森富氏もわたしたちに同行した。もしわたしの出社が一分遅れてい
たら、あるいは再会は実現できなかったかもしれなかった。(上の写真補足説明:左端の二人は駐日インドネシア大使館の職員)
わたしがマナイ・ソフィアン家に寄宿していたころ、子供は長女ソフィアと生れて間もない長男のソファンだけだったが、六人の子持ちになっていた。ソファンは既述のとおり著名人となり、インドネシアの百科事典 には親子そろって写真入りで載っている。
マナイ・ソフィアンには国連大使として赴任中に経験したちょっとした逸話がある。国連総会でスカルノ大統領が演説し終えるのをロビーに立って待っていたところ、突然一人の白人男性が彼に手を差しのべて、「閣下、こんにちは」と話しかけてきた。とっさのことなので、彼はびっくりして、ベチ(ソンコ帽)に手をやった。 彼はいつもスカルノと同じベチをかぶっていたので間違えられたらしい。その白人こそ時のイギリス首相ハロルド・マクミラン氏であったのである。
マナイ・ソフィアンは既述のとおり、旧ソ連駐在大使を最後に公職から身を引いたが、終始独裁的なスハルト元大統領を批判する立場を貫いた。彼と同じ立場の政治家や将軍をはじめとする著名人50人が、1980年5月にスハルトを批判する書を政府に提出した。これが有名な「五十人請願」でマナイ・ソフィアンも署名者の一人である。後に出国禁止者ブラック・リストに名を連らねた。なお彼は国会議員であった1952年 、国軍の組織改革問題で動議を提出して採択された。「マナイ・ソフィアン動議」として現代政治史に名をとどめている。彼はいつだったか、日本に行ってみたいという手紙をくれたが、その後出国禁止となって果たせず、現政権になって出国禁止は解かれたが、もはや老齢でそれも叶えられないであろう。
追記(2016-1-22)

写真上:1994年9月8日(金)付 Kompas 紙記事
"Manai Sophiaan 80 Tahun, Pejuang yang Kukuh dan Tetap Konsisten" より
Manai Sophiaan は80歳を迎えても意気盛んで、「9月30日事件」(G30S/PKI)の真実、そして盟友スカルノが事件に無関係であることを訴え続けている。Manai Sophiaan (写真中央)が彼の著書 "Kehormatan Bagi Yang Berhak" (初版本)を 友人 Roeslan Abdulgani (左)に渡しているところ、右は Manai Sophiaan の奥様
「長崎物語」の歌碑
わたしがセレベス新聞への出向でマカッサルに着いた翌日であったか、近藤三郎プワルタ・セレベス編集長宅で歓迎会を催してくれた。わたしはその席で、外語時代に覚えた流行歌「長崎物語」を余興に歌ったところ、同僚の花岡泰隆君がいたく感激し、引き揚げ後何年かして、月刊の毎日新聞社社報の随筆欄にその時のことを思い出して随筆を載せた。長崎物語という歌はその後はやり出したいわゆるお当地ソングの走りともいうべき歌である。作詞者は梅木三郎とあるが、実名はわたしの姓と同じ黒崎貞次郎氏で、毎日新聞社東京本社の社会部長をやったり、毎日新聞がオーナーとなったプロ野球パシフィック・リーグ毎日オリオンズの社長やパ・リーグ理事長をもつとめた多才の人物である。「空の神兵」や「戦陣訓の歌」も梅木三郎が作詞した歌である。
「空の神兵」は陸軍落下傘部隊がスマトラ島パレンバンに降下したのを知って、すぐさま作詞したとのことである。 花岡君の随筆を伝聞で知った梅木三郎(黒崎貞次郎)未亡人で歌手でもある水野重子さんはたいそう感激し、花岡君やわたしや長崎新聞東京支社長に助力を求め長崎市内に「長崎物語」の歌碑を建てるべく長崎市に働きかけたあげく、長崎市内オランダ坂に「長崎物語」の歌詞の一番「赤い花なら受珠沙華 阿蘭陀屋敷に雨が降る 濡れて泣いてるじゃがたらお春 未練な出船の ああ鐘が鳴る ララ鐘が鳴る」を刻んだ歌碑が建てられた。歌詞の執筆者は作家の井上靖氏である。
じゃがたらお春は実在の女性で、ジャカルタの資料館にもその事績を記した記録が残っている。わたしは「長崎物語」を歌ったり、聞くと、主に九州地方から南方に出稼ぎに行った、いわゆる唐行(からゆき)さんの哀話を連想する。わたしは昭和63年3月末、級友の石井、山中両君と三人組で九州旅行した折、昼食休憩時間をぬすみ、オランダ坂へこの歌碑を見に行き、碑の前に立って通りがかりの人にシャッターを押して貰って、その写真を未亡人に送ってあげて感謝の手紙をいただいた。
近藤三郎氏の自殺
プワルタ・セレベス編集長の近藤三郎氏は民族独立運動を積極的に支援したためか、オランダ側に捕らえられ収監されていたが、おのれの将来を予感してかどうか、はっきりした原因はわからないが自殺して果てた。一説には焼身自殺ともいわれる。近藤三郎氏については作家戸川幸夫氏の「昭和快人録」でもとりあげられている。勝尾金弥氏著「なぞのエス・コンドー」という児童向けの本もある。念入りな取材を纏めたもので近藤三郎氏のことを知る上で、たいへん貴重な書であると思います。

はじめての海外旅行 第3巻(インドネシア編)
「なぞのエス・コンドー」
著者 かつおきんや(勝尾金弥)
発行所 株式会社 リブリオ出版
1985年1月25日 発行
注:著者のご了解を頂き「八十年を顧みて」(平成13年10月25日発行)の一部をそのまま転載させて頂きました。(編集部)