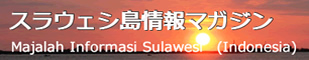 総目次 総目次 |
マカッサル清月堂物語
水原 庸光
銀座清月堂会長

当時マカッサルのトキワ通り
(現在 Jl. Ahmad Yani )
にあったマカッサル清月堂
セレベス島進出
昭和17(1942)年1月5日、私は海軍南方政務部の命を受け、猛暑のベトナム(当時の仏領印度支那)のサイゴンから初雪の名古屋港に、寒さにふるえながら帰国した。
第2次世界大戦の始まったばかりの頃である。
仏領印度支那サイゴン引揚げは現地代表(興南企業)に占領当初、何か不正があり、内地帰還命令を受け、私共と同行の各商社も同時に帰国するようになったのである。
帰国後、私は海軍受命業者の一人として蘭印(オランダ領印度支那)セレベス島マカッサル(今のインドネシア・スラウェシ島)への進出が決まったのである。
幸いに、二十三根拠地司令官は下村勝美中将であった。私の叔父の神谷と海軍時代の友人であったので、お宅でセレベス島赴任直前にお目にかかり、現地でよい菓子を作るようにとはげまされた。また、司政長官の東竜太郎先生も丁度内地に帰られた時で、東先生の親友の前田三介男爵の奥様からご紹介を頂き、石神井のお宅を訪問した。その日は帰国された日なのでベッドで体を休めていらっしゃったが、お目にかかる事ができた。その時、一言、寒天の製法を勉強してくるようにとのことで胸にジーンとこみ上げてくるものがあった。
また、すでに茅場町の喜可久の遠藤さんが、セレベスに進出されているので、留守宅にご挨拶に伺うと、運のよい時はまったく運のよいもので、丁度セレベス島ケンダリーの空軍司令官石川謹吾少将(後に中将)と情報局次長の久富さんがおいでになり、お目に掛かる機会を得た。菓子造りに渡南することを告げると、「それもよいが、菓子は中国人、メナド人も製造している。書籍の販売をする気はないか」との事で、早速日配(日本出版配給会社)の大橋専務をご紹介頂き、セレベス島、ボルネオ島の書籍の一手販売権をもって渡南する事になった。シンガポール、サイゴン等に黒馬堂という本屋が進出しており、邦人の各位から喜ばれている事を知っている私の心は一層ふくらんだ。
かくして菓子、喫茶、レストラン、書籍、ホテル、花の店、水原商会清月堂が誕生した。小生二十八歳の時であった。
その頃は敵の潜水艦が出没する時なので、途中、台湾の高雄で魚雷十三発喰い、九死に一生を得た。後継部隊の優秀な方が、私が乗船した同じ船で魚雷を受け死亡してしまったという話をきいた。
昭和十八年一月十日、日本を出て十四日後にセレベス島マカッサルに到着した。
菓子はクエ、魚はイカン、米飯はナシ
さてマレー語を全く知らない私が、船中でやっと覚えた言葉は、表題の「菓子はクエ、魚はイカン、米飯はナシ」だけであった。赤道直下のマニラ、バリックパパン、等を経て、世界一美しい夕陽のマカッサルに着いたときは実にほっとした。
港にある中国人の町から、一歩マカッサルの町に入ると、タマリンドーとロッテルダム(オランダの古い城)のある美しい静かな公園の中に町が発展したというような所であった。白馬や放し飼いの数十頭の山羊が遊んでいる。野生の猿や、白い鸚鵡や鶴が沢山飛んでいる。清新な緑と美しい空と海、一年中花が咲き、ガムランに明けガムランに暮れる町であった。
朝はコーランの祈りと鶏の鳴き声に目が覚める。バナナ(ピーサン)、パパイヤ、パイナップル、マンゴー、マンゴスチン、ランブータンの香りが町中に満ち満ちている。平和そのものである。戦争などまったく感じられない。同船の藤山一郎君の歌は、音楽好きのインドネシア人に大変な人気であった。
さて私は、どうしたら菓子の材料が集められるか、小豆に似た豆があるであろうか等等心配は尽きない。早速、パッサル(市場)通いが始まり、毎日まいにち、豆探しが続いた。そしてついに探し当てた。発見したのである。勿論小豆はなかったが、小豆に似た小型の丸い青い豆(カッチャン・イジョー)赤い豆(カッチャン・メラー)を見つけた。
マレー語の字引も全くないので下手な英語で話し、手振り身振りで取引する。市場はマカッサル語で普通のマレー語とは異なるので、初めは何を言っているのか聞き取れず本当に困った。
この豆から早速"ゴ"(豆汁)を取り、砂糖を加えると、全く内地の小豆の餡と同じ餡ができた。私は小躍りしてよろこんだ。嬉しかった。
「天は自ら助くるものを助く」とか「至誠天に通ず」という、なんとも云えない嬉しさがこみあげて、正直のところ助かったという気持ちであった。
西も東もわからず、まして言葉も通じない外国へ一人の店員をつれて乗り込んできた私は、いよいよ菓子工場の建設に取りかかった。これには唯一人の日本人の部下である和菓子の職人、稲盛茂の協力に負うところが大であった。工場建設は順調に進んだ。
私は通訳を一人雇って、はじめに17名の男女現地住民を集めた。マカッサル人、ブギス人、トラジャー、メナド、中国混血等の現地住民達である。
戦争中であり、前線である。私は彼らにこんな挨拶をしたのを覚えている。
「私は一天万乗の大君、天皇陛下の命を受け当地に着任したのである・・・・・・・云々」
驚いたのは通訳である。インドネシア語には王様にはラジャー、もっと大きい偉い王様はサルタンという言葉しかない。天皇とか、一天万乗の君などと云っても現地の住民には通じないと云う。それでは東洋で一番偉いサルタンといいなさい、と云って、吾々がアジア民族解放のための聖戦を行っていること、家族と離れ、身命を投げ出して君達のために戦っている将兵のお菓子をつくるために、私と稲盛がはるばる来たこと等を話し協力を求めたのである。
3ヶ月程して菓子工場も出来上がったので、まずはじめに羊羹を製造した。砂糖は1俵3円で経理部からもらった。民生部で買うと1俵7円50銭で倍以上の値段であった。寒天は相当量内地から運んだので、1ヵ年位は間に合う積りであった。
初釜の羊羹は、バナナの葉で船型を作りその中に羊羹を流し込み、白い半紙を3センチ位に切り「日の丸」を赤く染めて楊枝に巻き、旗を作ってこれにさした。出来上がった羊羹を持って現地の病院を訪問した。
内地はすでに物資の統制で砂糖などはないので、傷病の将兵の喜びようはたとえようもなく、また私の感激も言葉や文章では表現できないほどのものがあった。
今は亡き森田たまさんが、たまたま報道班として前線を慰問にきて、マカッサルの清月堂に来店、大福、饅頭、羊羹、珈琲、みつ豆を食べて、本当に喜んでくださったことが思い出される。
その後内地に帰られて新聞に、清月堂が現地で内地よりおいしい本物の菓子を造り、前線の傷病兵や兵隊さんに喜ばれていると書いて頂き、内地の父から手紙と共にその新聞を送ってもらった時は、今までの全ての苦労がふっとんでしまった事を忘れることができない。
邦人の各位が遊んでいる時にたった独りぼっちで働き、夜も広い倉庫の内で刀をだいて寝た数ヶ月は、時に月を見ては内地を偲び、ツバメをみては日本を恋しく思ったものである。
月日が経つにつれ、マレー語もだんだん話せるようになり、従業員も増え、喫茶、レストラン、書籍店、花の店のほかに、セレベス会館(中国料理)、海員クラブ等もやるようになった。
半年程して第二陣が鎌倉丸で出航した通知をうけ、今か今かと到着を待ちのぞみ、お蝶夫人のように、毎日港へ船を見に行った。しかし、ついに船は来なかった。フィリッピンとボルネオ島の間で、敵の潜水艦に撃沈され全員戦死してしまったのである。私の生涯を通じて、これ程悲しかったことはなかった。一人でも生存していてほしいと祈ったが駄目であった。私は独り埠頭に立って男泣きに泣いた。
バリックパパン進出
第三陣が書くごろ、ボルネオ島バリックパパン進出もきまり、従業員も一○○人程になり、花の店、セレベス会館も書籍店も順調に進み、邦人、現地の住民の信頼も得、仕事も拡大していった。白人の捕虜の食パンを製造したり陸軍の御用もするようになった。また、セレベス新聞(毎日新聞)のハジ近藤氏から委嘱され、インドネシアの「いこいの泉」という王様だけが泊まれる小さなホテルの経営をまかされたのもこの頃であった。
知遇を得た方々
緒方商店の緒方さん(緒方竹虎さんの実兄)金子支配人、南洋興発、南太平貿易の松江さん、瀬川さん、マカッサル市長の山崎さん、三井物産の峯さんと鎮目さん、城さん、パレパレの牧野氏、当時の邦人授業団の団長は三菱の川奈さんで、私は八十五番目に進出した一番小さ受命業者であった。
マカッサル総監は岡田文秀氏、山崎微氏、東龍太郎氏は司政長官、前尾繁三郎氏は会計課長、江口美留氏は官房長、西村直巳氏は文書課長、高橋善磨氏は商工課長、マカッサル研究所長は園部一郎先生、桐野大佐、マカッサル病院長東一先生、日銀副総裁澄田さん、総務局長富永少将、宮内庁式部宮長の湯浅さん、石田大佐等そうそうたる方々であった。
また、インドネシア独立運動の志土、吉住隊の吉住氏、ハジ近藤(毎日新聞)花機関(花田少将)佐々木、庄司の両君、民政運航会の新田目氏、興南組のパプア金子氏、木工所の久保田氏、上田パンジャン、新南興業の森キャンビン氏、方和の矢館氏等、私は大倉山の山本麟太郎先生の弟子の故をもってこれ等の方々の知遇をすぐに得た。その他、海軍の山本英輔北将、山本方閣下の奥様、横山雄(A級戦犯になたが)、またアメリカのルーズベルトや、国務長官ポプキンス等と親交のあった金子健太郎伯爵並に桑島寿雄氏、頭山先生の親友岡本人吾氏、仏印大南公司の松下さん、司死政長官千田牟呂太郎氏、銀座菊水の内藤様等々、いろいろなお方から御苦情を頂いた。
爆撃下の菓子造り
何といっても一番こまったのは言菓であった。宗教、習慣、食物にもだんだん慣れてきたが、なかなか慣れてくれないのが言菓であった。はじめは買物するにも、電話一つするにも不自由であった。
戦況が次第に悪くなるにつれ物資が不足してきた。毎朝十時頃になると、必ず空襲があった。すると現地住民の使用人達はみんな山の中逃げて行ってしまい、工場では餡がこけて使いものにならなくなることも、しばしばであった。敗残の色はますます、濃くなるばかりであった。
トウヨロコシしかない時は、トウヨロコシの干パンを、砂糖しかない時は、ドロップを、タピオカしかない時は、タピオカの粉で羽二重餅をつくった。この羽二重餅は、まったくすばらしい光沢で、その味は最高であり、日本の"求肥"よりも美味しく、われながら自慢の出来栄えであった。
紙寒天の製造
しかし菓子の受命業者として一番困ったのは寒天がなくなり、暑さに耐え、日持ちのよい羊羹が出来なくなった事で、東龍太郎先生が、寒天の製法を習ってくるようにとおっしゃった事が、ようやく解ったのである。手持ちの寒天を使い尽し、マカッサルの中国街の寒天を買い占め、セレベス全島の寒天を集荷したのが民生部に知れ、買占めはいかんと注意を受けた。今後は民間の手で寒天を製るようにとの事で、三井、三菱、緒方、水原商会 の四社が現地で製ることになった。しかし鱶がたくさんいる海で、どんな海藻から寒天質のものをとるか誰にもわからず、結局、東子に直接関係のある水原商会清月堂のみが寒天づくりに励むようになった。あとで考えると結局コスト高で、大きな商社はわずかな寒天など製らなかったのだと気が村いた。
私は全店員を集め、清月堂の使命は菓子造りこあること、そしてそのためには寒天の製造法を調べて来いといったのだが、誰も自信がなく、私がやることになった。
先ず密偵を山に派遣し、かくれているアンボン人のキリスト教の牧師から、昔どのように海藻から寒天をとったか調査させた結果、プルーキャンビン、サゴサゴ、アガルアガルからとった事で、早速仕事にとりかかった。現地では寒天の代名詞がアガルアガルである。
海に入りたがらない現地の住民に二倍の賃金を払い、ようやくアガルアガル、サゴサゴ、ブルーキャンビンの三種を集め、半年の間、本当に命がけで、この製作に熱中した。霜枯れの日本の製法は、暑い現地では全く通用せず、はじめ製氷会社の中で製った。何十回やっても寒天が出来ず失敗に失敗を重ねた。
しかし、ある夜私は夢を見た。それは日本でみたゼラチンが網の目となまこのようにうねっている夢であった。はっと気がついて飛び起きた。早速、木の枠を造り、サラシ布を敷いて寒天液を流し、太陽の光線に当てると、みるみる内に水分が蒸発し、ボール紙のような寒天が出来上った。しかし、下部の水分がどうしてもとれないので、司令部に行き、機関参謀に会い、寒天の重要性を説き、トタンがあればきっと成功すると私の熱意を告げ、爆撃でこわれた港付近からナマコ型トタン板を貰うことの許可を得た。
早速下の方にトタンを敷いて何回も実験を重ね、見事に立派な紙のような寒天の製造に成功した。私の生涯で最良の喜びは、この寒天製造の成功に勝るものはない。涙をどうしてもとめる事ができず、泣きながら民政部長石田大佐のところにその寒天に砂糖とエッセンスを加え、ゼリーのような菓子(金玉)を持って報告に行った。
石田大佐から「よくやった」とおほめの言葉を頂き、労をねぎらわれ私は万事、人間はの努力によって必ず報いられるのだと思うと同時に、何か人間の力以外の大きなものを感じた。
砂糖しかなくなった時はドロップを製った。しかしドロップの着物であるが、和紙で包むと、特に雨期には紙がベトついて飴からはがれない、悩んだ。ある朝のことである。タマリンードーの実を現地の住民が拾っているのを見て、「あれは何にするのか」と聞くとアッサム(スッパイ)ですと言う。その時もインスピレーションがひらめき、早速そのを加えると紙が前よりベトつかなくなったのを覚えている。これ天佑であろう。
小さなピーサン(バナナ)に生命を救われて
私がいま、毎日幸せに暮せるのは、たった一本の小さなピーサン(バナナ)のお陰である。
次第にに戦争は激しさを増し、島の状況は日を追って悪化していった。美しい夢の島も爆撃を受け、昭和二十年八月十五日、終戦を迎えることになった。天皇陛下の玉音放送を聞いたのは翌日であったが、無条件降伏と知って在留邦人はみんな泣いた。連合軍の上陸は二カ月後だったので武器を一カ所に集め、日の丸の旗を焼いて覚悟を決めた。この時、生きで祖国の土を踏めるとは考えてもみながった。万が一、生き延びられる仲間がいたら、立派に働いたことを祖国に伝えてほしいと仲間同志泣きながら語り合った。
敗戦後ついに連合軍が上陸し、林兼の工場に収容された。一日二食の粗末な食事をあてがわれ、畑を耕し木を切るなどの重労働をされられた。力のない私は筆舌に尽くしがたい苦労をした。もちろん外出は禁止されたが、私は食料隊長をしていた関係で、町に食料を買い出しにいく役目をされられた。同じ棟に七十人ほどの民間企業の社長が収容されていた。食事ともなると一羽の鶏を七十人で食べることになるわけで、十人ほどの炊事夫が無残なまでにそれを食べてしまう。鶏飯と言ってもみんなの食事はただ残りの脂が浮いているだけ。それでも「今日は鶏飯だよ」とドラムかんを叩くと、ワーッーと歓声を上げて社長たちが集まって。恥も外聞もあったものではなかった。
やがて私達民間の者はマカッサルから七○キロも離れたマリンブンに移され、そこで農耕を強いられた。不毛の土地で、大根を植えても五センチから十センチ程のものしかできず、じゃがいもやナスも、せいぜい親指大位にしか育たない土地であった。
炎天下の重労働と粗末で少ない食事のため、仲間達はみるみる痩せ衰えていった。
インドネシアの暴徒がでるので、豪州兵が武装して守ってくれた。周囲を川に囲まれたこの土地は何回となく暴徒に襲われ夜襲が続いた。殺される者、自殺する者、発狂するものが出る極限状態に陥った。
私も毎日使役に使われ、いつかは死んでゆくであろう。いつその事、自分で死んだ方がましであろうと一日二杯の飯を絶つことにした。断食して四、五日経つと、目立ってやせてきた。丁度その時デング熱で四○度位も熱発したが、誰もみてくれるわけでもなし、自分でただ死を待つのみであった。
ふと床下を見ると一センチ程のピーサン(バナナ)の芽が生えていた。翌日は二センチ程に伸びていて、数日の内には十センチ位になった。水だけ飲んでいた私は、翻然として気がついた。
このピーサンの芽は何のために生きているのであろう。誰も教えぬのに植物は花を咲かせ、実をつける。人間は一体何のために生れたのか、花も咲かず実もつかず、今死んでたまるか、とその時気がついた。天の声とでもいうのであろうか。私は内地に残した妻子の事をこの時はじめて想い出し、何としても生きょうと、それからもりもり食事した。内地の土を踏むまでは内地の子供達に逢う迄はどんな事をしても生きょうと。
生水はセレベスでの五年間一度も飲まなかった。もし生きて日本に帰れたら、なにより先に水を飲もうといつも考えていた。朝、水を汲みに行くと、残月が水に映って揺れている。月は故郷を思い出させた。「ああ、渡り鳥になって日本へ帰りたいなあ」としょっちゅう思ったものだ。
そして私は今、こうして生きている。
一本の小さな植物の芽に救われて、神仏に心から感謝している次第である。
苦しみの多かった戦中戦後のセレベスもいまでは懐かしく思い出される。苦しみの一方では、もと衆議院議員、前尾繁三郎さんやもと内務大臣、山崎巌さん、もと文部次官、岡田文彦さんなど、多勢の方々のお世話になりその親切は忘れることができない。当時の方々で現役でご活躍の方に日銀の澄田総裁や第一ホテルの秋田社長がおいでになる。
一昨年、二十八年ぶりにマカッサル(ウジュンパンダン)を訪れれた。一番嬉しかった事は私が当時製った前述のタピオカ粉の菓子が店頭で売られており。現地の林兼の社員の方から「水原さんの製った日本菓子が唯一つ残っておりますよ」と云われたことである。
これこそ、私の生涯を通じて最高にうれしかったことであり、これこそ私の今迄の苦労に花が咲き、実が結んでくれたのだと心から感謝している。
掲載日:2005年1月17日
Copyright (c) 1997-2020, Japan Sulawesi Net, All Rights Reserved. |