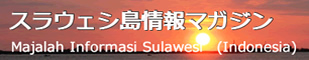 総目次 総目次 |
鯨を食べよう(1)
長崎 節夫
鯨と日本の開国
幕末の嘉永6年(1853)、アメリカのペリー提督が軍艦4隻を率いて東京湾口(浦賀沖) に現れ、徳川幕府に開国を迫りました。これまで見たこともない大型軍艦による威嚇に、日本中が上へ下への大騒ぎぎとなりました。 この、ペリー提督による開国要求の⼤きな目的は、日本近海で操業するアメリカ捕鯨船への、 食料、飲料水、薪などの補給にありました。
当時のアメリカ式捕鯨の様子を、私たちはハーマン・メルヴィルの小説「白鯨」によって伺い知ることができます。アメリカ式捕鯨は⼤型の帆船に捕鯨用の端艇(カッター)を数隻積みこみ、漁場ではこの端艇に捕鯨銃を携えた射⼿が乗り込んで鯨(主にマッコウクジラ)を追いかけ、銃で仕留めます。メルヴィル自身が捕鯨船乗組員として日本近海まで来たそうです。そのときの⾒聞を元にして著したのが、小説「白鯨」というわけです。
幕末のころの日本近海は、はるばる太平洋を越えてやってきたアメリカ捕鯨船の草刈り場な らぬ、クジラ狩り場でした。アメリカの捕鯨基地は北アメリカ大陸の東海岸側(大西洋岸)にあります。日本近海漁場にむかうためには母港を出発したあと大西洋を南下して南米大陸の南端を回り(パナマ運河はまだできていない)、今度は南米大陸の西岸に沿って北上、赤道付近で西に向きをかえ、太平洋を横断して日本近海に向かうという、気が遠くなるような長距離航海です。アメリカの母港を出発し、操業を終えて母港に帰り着くのに大体2年半を要しました。
捕鯨船は仕留めた鯨から油を煮出しますが、鯨の脂皮を煮るのに薪を使います。長期の航海ではどうしても薪が不足する。食料、飲料水も不足。特に、生鮮食料の不足は深刻です。乗組員のビタミン不足からくる壊血病は、アメリカ捕鯨船にとっては常に悩ましい問題でした。飲料水も長期の航海ではどうしても不足気味になります。残存水は腐りかけてくる。目の前にある日本の港で新鮮な水・食料、薪などを補給できたらどれだけ助かることか。
また、夏は台風の接近、冬は季節風の吹き出しと、気象条件の厳しい日本近海ですから、遭 難事故もおこります。遭難捕鯨船の救助や、船員の本国送還などのために日本の助力がほしいところです。アメリカが力ずくで日本に開港をせまった気持もわからないではありません。
ペリー艦隊の来航により日本では、殿さまクラスから足軽階層まで攘夷熱に感染・発症する 者が続出しました。なかでも過激に反応したのが水戸、長州、薩摩です。長州藩は薩摩藩とともに攘夷運動の先頭を突っ⾛って、行きついた先が「明治維新」というわけです。
歴史教科書ではペリー提督が日本に開国を迫ったことになっていますが、実は、陰の主役はクジラであったという、ウソのようなホントの話です。
アメリカ捕鯨にまつわる逸話をもうひとつ。
江戸時代末期、土佐・中の浜の少年漁師が遭難。小笠原諸島ちかくの鳥島に漂着していたと ころを、たまたま島に寄ってきたアメリカの捕鯨船に救助されました。捕鯨船の船長は、この若い漁師をアメリカに連れ帰り、養子として学校教育を受けさせます。数年後、流暢な英語を話せるようになった青年は日本に戻り、幕末から明治維新にかけて対米外交に、あるいはアメリカ式捕鯨の導入に活躍しました。
上は日本人のほとんどが知っている逸話ですが、当時の日本近海がアメリカ捕鯨船の活動領域であったことを裏付ける話です。(アメリカ捕鯨の最盛期には約350隻の捕鯨船が⽇本近海に出漁していたそうです)
日本の捕鯨(概略)
縄文時代から現代にいたるまで、私たち日本人は鯨を食料として利用してきました。とくに
江戸時代以降は捕獲技術も発達し、不十分ながらもそれなりに販売網も広がって、鯨は日本人の重要な食料となりました。調理法も進歩し、とにかくアタマの先からシッポの先まで、ほとんどの部位が食用として利用されました。食べられないヒゲや骨は工芸用の材料になります。
100%利用、捨てる部位はありません。
日本の伝統的な捕鯨は、地先に寄った鯨を数隻ないし十数隻の小舟で浅瀬へ追い込み、銛を
投げ、長刀でとどめを刺すという、ほとんど原始的かつ勇壮な漁法でした。江戸時代にはこれを少し進歩させて、網をからませて鯨の行動の自由を奪う「網取り式」が考案されましたが、目の前にやってきた鯨を多くの小舟で追い詰めるということで、基本的には変わりません。
他の産業もそうですが、捕鯨業も近代化が進んだのは明治以降です。捕鯨銃という飛び道具を取り入れ(アメリカ式捕鯨)、続いて、銛を打ち出す捕鯨砲を備えるようになり(ノルウェー式捕鯨)、船にエンジンを備えて遠洋に乗り出し、昭和時代に入ると、ついに鯨の宝庫・南氷洋まで進出しました。以後、捕鯨といえば南氷洋捕鯨を指すほどになりましたが、第二次大戦で中断します。
敗戦直後、大洋漁業(現・マルハニチロ)の社長・中部幾次郎は、食糧不足打開の途は南氷
洋の鯨にあると思い立ち、占領軍のマッカーサー大将に捕鯨船団の南氷洋出後許可を願い出ました。マッカーサーはこれを承諾し、念願かなって昭和21年(1946)南氷洋捕鯨が再開され、クジラは戦後日本の食糧事情を大いに援けました。
昭和30年代中頃、南氷洋捕鯨は最盛期をむかえます。捕鯨といえば日本の花形産業でした。
毎年、秋口になると大洋漁業はじめ日本水産、極洋捕鯨と、日本の大手水産会社の捕鯨船団が日本を出発して南氷洋に向かいました。⽇本の冬季(南氷洋の夏季)に南氷洋で鯨を捕獲し、桜の季節になると日本に帰ってきます。その出港・帰港の光景や、南氷洋での捕鯨船の活躍ぶりは、ニュース映画や少年雑誌のグラビアなどで常連ネタでした。わが日本に捕鯨船団あり。
当時の日本の男の子たちにとって、捕鯨船団は、敗戦で消滅した連合艦隊に代る日本の誇りのような存在であったかもしれません。現代で言えばオリンピック総合優勝の期待がかかる日本チームのような存在、というところでしょうか。何しろ金メダル確実、持ち帰る獲物は何万トンもの鯨肉でしたから。
昭和30 年代後半、私は世田谷・三軒茶屋や横須賀、浦賀方面を縄張りにして生きていまし
たが、クジラ食は貧乏学生にとってささやかな贅沢でした。気の利いたレストランには大体、
クジラ系のメニューがありました。昼食はほとんど外食でラーメンまたはうどんというところですが、たまに懐具合によっては少し気張って鯨カレーや鯨カツなどをいただきました。当時、学生が気軽に出入りするような食堂に、トンカツやビーフステーキのメニューはありません。
クジラは豚や牛の代役であったかも知れませんが、十分美味しくいただいていました。
時は流れて平成26年10⽉、大貫さんの案内で50年ぶりにクジラ料理と再開しました。 実に半世紀もの間、⼀切れの鯨も食べていなかったのです。
国際捕鯨委員会(International Whaling Commission)
なぜ、私の目の前から鯨が消えていたのか。原因は、人間が鯨を獲りすぎたことです。19世紀、 帆船時代のアメリカ捕鯨から始まって、20世紀半ばまで、アメリカ、イギリス、ノルウェーなどの捕鯨先進国、あとから参加した日本などが派手に獲りすぎたのです。そのことに気が付いた関係各国は国際捕鯨条約に基づいて、鯨資源管理のための国際捕鯨委員会(IWC)を設置しました。(1948 年設立。日本の参加は1952 から)
IWC 設置の目的はクジラ資源の適正な管理を図ろうということですが、当初、その運用は全 くクジラ資源の実情に合わないもので、肝心のクジラ資源はどんどん減少し、シロナガスクジラなど⼀部の大型鯨類は絶滅の危機に陥ってしまいました。その流れで出てきたのが、捕鯨モラトリアムです。クジラの捕獲を中止することによって、クジラ資源の回復を図ろうというわけです。 同時に「調査捕鯨」の実施も取り決められました。鯨の資源状況や生態などを科学的に調査・検証して、今後のクジラ資源管理に役立てようというわけです。日本はIWCに調査捕鯨の実施を申請し、承認されました。
アメリカなど、畜産国の陰謀
IWCで捕鯨モラトリアムが可決されたのは1982年です。30余年経過した現在、⼀部
のクジラ資源(ミンククジラ、マッコウクジラ等)は商業捕鯨の再開も可能なほど⼗分に資源が回復していると判定されています。特にミンククジラなどは増えすぎているほどで、他の漁業への影響が問題になっています。
しかし、(IWC管轄内での)商業捕鯨再開のメドはたっていません。再開どころか調査捕鯨さえも継続できるかどうか危ぶまれています。
現在、IWC(国際捕鯨委員会)メンバーのなかで捕鯨反対を主導しているのはアメリカとオーストラリアです。その他、アメリカに同調したヨーロッパ諸国、ニュージーランド、南米諸国などが反捕鯨の立場です。アメリカは、捕鯨とは全く関わりのない国々をIWCメンバーに引き入れて反捕鯨勢力を増やしています。
商業捕鯨再開(もちろん条件付きで)を主張しているのがアイスランド、スペイン、日本は
じめとするアジア諸国(中国は中⽴)、アフリカ諸国、ミクロネシア・マーシャル諸島など太
平洋の国々です。
捕鯨再開派と反捕鯨派の対立。これは煎じ詰めれば、クジラは食べ物(食料)であると主張
している国々と、クジラは食べ物ではない、保護すべき動物(ペット)であると主張する国々との対立です。再開派の親玉は日本、反対派の親玉はアメリカです。
アメリカやオーストラリアが「クジラは食べ物ではない」と主張するのは、ある意味、当たり前とも言えます。
アメリカは歴史的に見てもクジラを人間の食料として捕獲していたわけではありません(ア
ラスカの先住民が食用としている例外あり)。彼らはクジラを「油を採るための原料」として
捕獲してきました。技術が進歩した現在、油はクジラからではなく、地面の中から効率的に取り出すことができます。油の原料としてのクジラはもういりません。
また、アメリカやオーストラリアという国は、広大な農地を有し、大規模な畜産業が国の経済を支えています。国民は牛や羊、豚の肉が常食です。クジラなど食べなくても痛くもかゆくもない。クジラは食べ物だなどと思ったこともないでしょう。
それに、牛や豚などの畜肉は自国民の食糧であるだけでなく、日本だけ確実に日本向けの畜肉輸出量が減ります。「ここは屁理屈を並べてでも日本の捕鯨再開を阻止しなければならない」と決意しているに違いありません。
その昔、アメリカ海軍のペリー提督はお国の捕鯨船のために日本に開国を迫りました。現在はお国の畜産業のために日本の捕鯨再開を阻止しているということでしょう。
クジラを食べよう
しかし、国民のタンパク食料を海に頼っているような日本をはじめとする多くの島国、さらには漁業も畜産業もままならないアフリカ内陸部の貧しい国々が、アメリカやオーストラリアなど畜産大国のご都合で食料補給の途を制限されなければならないというのは、とうてい納得できかねることです。
現在、アフリカのいくつかの国では食料不足で子供の発育不良や餓死が問題になっています。 日常的に牛肉をたらふく食っている国々では想像もつかないことかもしれません。 突飛な提案ですが、クジラはアフリカの貧民を救う救援食にもなります。日本は国連分担金 を半分に減らして、その浮いた予算でクジラ缶詰をアフリカの貧困地域に送り、飢えた⼦供たちの栄養補給にあてたらどうでしょうか。わけのわからない国連とかに多額の上納金を納めるより、アフリカの子供たちを救うほうが、よほど⼈類への貢献になるのではないでしょうか。
しかし、人類への貢献を考える前に、私たち日本人にも課題があります。 私自身が50年ぶりに鯨肉を食したことからわかるとおり、日本人⼀般が鯨食から遠ざかっ ていることが重大な問題です。鯨肉は栄養価からみても食の安全面からみても、陸上で生産された畜肉などよりはりかに上質・安全なタンパク食糧です。捕獲する種類・数量をきっちり管理して利用すれば、永遠に続く⼈類の食糧源です。その食糧源をアメリカとか、どこかの環境団体のプロパガンダに乗せられて、日本人自体がクジラをペットだと思い込むようになってきました。人間、それぞれ好みがありますから、クジラでもワニでもペットと思うことはそれでかまいませんが、食べ物だということを忘れては困ります。忘れたことは思い出すこともできるからまだしも、若い世代は生まれてこの方、クジラなど食したことがない⼈が多いでしょう。
クジラが食べ物であるという認識をハナから持っていないと思います。 クジラが貴重な食料資源であるとしても、食べたいと思う人がいてこその食料資源です。国民がクジラを食べ物として認識しないようでは話になりません。 捕鯨関係者、とりわけ担当官庁である水産庁には、クジラ食普及にしっかり取り組んでもらいたいところです。 現在、本格的な商業捕鯨の再開はむつかしい状況にありますが、全く何もできないというわけではありません。モラトリアムの対象外となっているクジラもあります。また、小型沿岸捕鯨などは国際規制の対象外で、日本の国内法で操業ができます。IWC管轄下の調査捕鯨もふくめて、1頭でも多く鯨を捕獲し、一人でも多くの国民(もちろん外国からのお客さんにも)に提供してもらいたい。捕鯨妨害活動で来日する環境保護団体のメンバーにも、おいしいクジラ料理をふるまってはいかがでしょうか。あまりの美味に認識をあらためて、捕鯨再開派に転向するかもしれません。
下関、東京大阪の大都市、高知市、太地町などクジラ料理を提供するレストラン、居酒屋な どは結構あるようです。会員の皆様も機会がありましたら“率先して”クジラメニューを試されるよう、お願いいたします。(完)
参考資料
- 小松正行「日本の鯨食文化」祥伝社新書