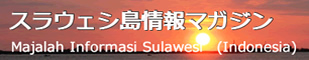 総目次 総目次 |
鯨を食べよう(2)
長崎 節夫
2018年12月20日、インターネットニュース、テレビニュースなどで「日本政府が国際捕鯨員会(以下、「IWC))を脱退の方針」と報じられました。続いてクリスマス明けの26日には菅官房長官が記者会見し、日本政府として正式に「IWCを脱退する」と発表しました。
このニュースを受けて、マスコミ各社や捕鯨関係者に野次馬も交えて賛否両論沸き上がりました。
鯨を食べよう(1)でも触れたとおり、現在のIWC内部では、商業捕鯨再開をめざす国々(捕鯨国)と、このまま永久に捕鯨を禁止したい国々(反捕鯨国)が対立しています。問題の根っこになっている商業捕鯨一時停止(捕鯨モラトリアム)は、1982年のIWC年次総会で議決されました。この捕鯨モラトリアムの本来の目的は、「捕鯨を一時停止」することによって、これまでの乱獲で減少しているクジラ資源の回復を図ろうということでした。
あれから約30年、日本はじめ関係国の資源調査活動によって、ミンククジラなど一部のクジラは資源が十分に回復していることがわかっています。それなりの秩序を保って捕獲すれば十分に商業捕鯨は成り立つということで、近年はIWC総会のたびに日本など捕鯨国側から捕鯨再開案件が提議されるようになりました。それに対し、アメリカなど反捕鯨国は、「資源量が問題ではない、クジラを捕獲するか保護するかが問題なのだ」と、モラトリアのム設定当初の論点を動物愛護の問題にすり替えて、結局、数の力で捕鯨再開の要望はつぶされ続けているというわけです。
今年(2018年)9月、ブラジルで開催されたIWC年次総会では、日本側代表団は捕鯨再開の決議を勝ち取るべく、例年より参加陣容を強化して臨みましたが、アメリカを中心にした反捕鯨国の厚い壁をやぶることができませんでした。マスコミ報道によれば、この年次総会が終わった時点で日本政府はIWC加盟のままでは商業捕鯨を再開することは不可能と判断し、IWC脱退の意向を固めたようです。IWCを脱退しても国連海洋法関連の制約があって日本単独で勝手に商業捕鯨を再開することはできないそうですが、日本政府としては何らかの成算があるのでしょう。
「日本政府、IWCを脱退して商業捕鯨再開を目指す方針」というニュースを聞いて、とっさに思ったことは次の二点です。
一つは「ついにやったか」という思い。日頃から、捕鯨に関してはいつも反捕鯨連合軍にいいようにやられて、このままでは勝ち目はないと感じていました。日本が捕鯨再開を目指すなら何か思い切った策(例えばIWC脱退とか)をとらざるを得ないだろう、と思っていました。
もう一つは、アメリカが主導する国際機関(IWC)から日本が足ぬけすることに対する(軽い)驚きでした。敗戦後70年余、アメリカ抜きでは呼吸すらできなかったほどの日本国です。簡単に「抜ける」と言って大丈夫だろうか。これから欧米相手の外交関係で嫌がらせを受けるのではないか少々心配でもあります。しかし、政府が破れかぶれで脱退を発表しているわけでもないだろうし、それなりの目算があるのでしょう。
昨年(2017年)、環太平洋経済連携協定(TPP)の枠組みからアメリカが足ぬけしました。その後日本主導で作業を進め、今年(2018年)末ぎりぎりにとりあえず(11か国のうち)6か国の発効にこぎつけました。残り5か国もそれぞれ各国内での条約批准を終え次第、正式に協定参加の予定だそうです。この事実は‘アメリカ抜きで(日本国が主導して)’国際協定締結を進めたという珍しい事例になります。TPPの場合は親分アメリカが途中で変心(乱心?)して脱退したために番頭格の日本がひと踏ん張りしてまとめあげたという構図ですが、国際関係の中で日本がこのようなリーダーシップを発揮したということは、これが初めてではなかろうか。
そして今回のIWC脱退です。敗戦後70余年を経て日本も少しは成長し、曲がりなりにも自立の意識が芽生えてきた、ということでしょうか。
b. 西洋の捕鯨事情―ノルウェー
地球の裏側西洋にも、日本と同様に古い時代からクジラを食用として利用してきた国々があります。代表的なのがノルウェー、そしてアイスランド、グリーンランドなどです。イギリスも昔は捕鯨国で、南氷洋捕鯨の最盛期には船団を仕立てて南氷洋まで遠征したものですが、現在は親戚アメリカと歩調を合わせて反捕鯨国になっています。
現在、大西洋側で商業捕鯨再開に執念を燃やしている国はノルウェーとアイスランドです。ノルウェーは言わずと知れた捕鯨の先進国で、歴史的にも世界の捕鯨業をリードしてきました。現在一般的に行われている、捕鯨船の船首部に大砲を据えてクジラを撃ち仕留める捕鯨技術はノルウェーが発祥の地で、日本もそれに追随しています。
1982年に南氷洋捕鯨の一時停止(捕鯨モラトリアム)が決議されたとき、ノルウェーはもちろん反対の立場でした。「商業捕鯨は何とか続けたい」ということで、捕鯨モラトリアムに異議申し立てをして(賛成しないで)、IWCは脱退しないで北大西洋の商業捕鯨を続けています。ノルウェーはIWCによる捕鯨禁止の決議に“同意しないことを表明”して商業捕鯨を続けているのです。この捕鯨モラトリアムは多数決に従わなくてもよいということです。商業捕鯨を続けると言っても、最大の漁場・南氷洋は全面捕鯨禁止(調査捕鯨は除いて)ですから、ノルウェーの捕鯨船は自国近海で細々と捕鯨を継続し、捕獲した鯨肉の一部は日本に輸入されています。
実は、わが日本もノルウェー方式(禁止に同意しないで)で商業捕鯨を続けることを考えましたが、親分アメリカから「そうであれば日本トロール漁船によるアラスカ沿岸での操業を許可しない」という対抗策を示されて降参しました。
当時、日本の遠洋トロール漁業がまだ健在で、特にアラスカ沿岸はトロール漁業の重要な漁場でした。アラスカ沿岸のタラを確保する引き換えに南氷洋のクジラを諦めることにしたわけです。しかしその判断は、結果から言えば大間違いでした。そのころからくすぶり始めていましたが、海洋管理の分野で「排他的経済水域」という考えが出てきました。各国が目の前の海を‘排他的に’管理することができるという考え方です(別名、200カイリ経済水域)。アメリカは早速、アラスカ沖にもこの新しい秩序を適用し、日本のトロール漁船は閉め出されました。鯨の代わりに確保したはずのアラスカ・タラ漁場は何だったのか。(ノルウェーの話がアラスカに跳んでしまいました)
c. アイスランドとクジラ
ノルウェーの西方、北海のほぼ中央にアイスランド共和国があります。共和国の主島・アイスランド島の中心部は北緯65度,西経17度ですから北極圏に近く、火山、温泉、氷河が売り物の観光地です。アイスランド島の面積はおおよそ北海道と四国を合わせた面積とのことですが、人口は約34万人。数字だけみると過疎地で土地がいっぱい余っているという感じですが、陸地のほとんどは火山性の岩石に覆われた険しい山地で、人が住めるような環境ではありません。住民は海岸沿いの狭い平地に住んでいるので、その部分は結構な人口密集地になっているそうです。
島の南側に、幅約100キロ、奥行き50キロほどの大きな湾があります。外側からみて湾の右手の奥に首都レイキャビク市があります。つまり、レイキャビクのななめ前には広大な湾が広がっている形になります。この湾は古来、鯨の集まる場所として知られ、8世紀ごろ、アイスランドがまだ無人島の時代からノルウェーの漁師たちがクジラ漁に来ていたそうです。湾の名称もそのものずばり「クジラ湾」です。
ノルウェー漁民のほかにアイルランド、グリーンランドからの移住者もあって、彼らが現在のアイスランド国民の始祖であります。
現在のアイスランドはその特異な景観(火山、湖、氷河)でもって人気の観光地になっており、欧米やアジア各地、もちろん日本からも多くの観光客がやって来るそうです。観光のお目当ては陸上の自然景観と海上(くじら湾)のホエールワッチング。
ところで、ある調査機関がレイキャビクの(ホエールワッチングの)観光客にアンケート調査をおこなったところ、20%の客がレイキャビクのホテル、レストランなどで鯨を食したと答えたそうです。何しろ歴史始まって以来の捕鯨国です。クジラはアイスランド国民にとって日常的な食糧であり、観光客がホテルや町中で普通にクジラ料理を食べることができる環境にあるわけです。普通の観光客にとっては、泳いでいるクジラを見物するのと料理されたクジラを食べることとは矛盾することではないのでしょう。賛成か反対か、どちらか一つを選ばなくてはいけないということはない。私だって、泳いでいるクジラを見物するのは好きだし、クジラ料理も大好きです。レイキャビクでクジラ料理を提供するレストランは年々増える傾向にあるそうです。この状況に危機感を持ったグリーンピースなど環境保護団体(反捕鯨団体)は「クジラを食べるな」キャンペーンに一段と熱をあげているとのことです。有史以来のクジラの島で「クジラを食べるな」と言うのも無茶な話ですが、原理主義者たちは無茶を承知で自分の価値観を他人にも押し付けるのでしょう。
ところで、レイキャビクの眼前に広がる「クジラ湾」ですが、アイスランド政府はこの広大な湾(幅100キロ奥行き50キロ)をほぼ二つに分けるように線を引いて、陸地寄りの半分はホエールワッチングエリア、外側半分は捕鯨可能なエリアとして区分しました。ある時期、捕鯨に消極的な政党が政権を握った結果、湾の中央に引かれた分割線は外側にずらされた(つまりホエールワッチングのエリアが広がった)そうですが、 また元の政権に戻って分割線も元の位置に戻されたそうです。
人間が勝手に海の上に線を引っ張って、こちら側はワッチングのエリア(捕鯨禁止)、向こう側は捕鯨可能エリアと決めつけ、当のクジラたちにはそのことが伝えられていません。今しがた環境客の目の前を泳いでお客さんを楽しませていたクジラが、何分か何時間か後には向こう側(捕鯨エリア)を泳いないとは限りません。そこで捕鯨船に見つかって、ズドンと一発喰らう可能性があります。クジラは明日の晩あたりにステーキになってテーブルに運ばれ、お客さんを喜ばせる、ということも起こり得るわけです。
d 沖縄のイルカ漁
地球のこちら側、日本列島の最南端沖縄にも1950年代の一時期、(沿岸)捕鯨業がありました。当時は捕鯨ブームともいえるほど日本全国的に捕鯨業が流行りました。南氷洋だけがクジラの漁場であったわけではないのです。
そのような時代の中で、米軍統治下の沖縄にも小型捕鯨漁船を使用する捕鯨業が導入されましたが、私が物心ついた1960年代には捕鯨業そのものは消滅していて、鯨を浜辺の水際から処理施設まで引き揚げる斜路だけが残っていました。というわけで私は当時の沖縄の捕鯨についての記憶はほとんどありません。
私がこれから書くのは、漁業(事業)として行われていた捕鯨のことではなく、沖縄県名護町(現在は名護市)でお祭り的に行われていたイルカ漁のことです。
沖縄・名護町(現名護市)の前浜に寄せてきたイルカの種類は不勉強でよくわかりませんが、とにかく毎年、春になるとイルカ便りというか、新聞ラジオで、名護の浜にイルカが“寄った”というニュースが流れた。
「名護湾」は近頃有名になった名護市辺野古とは背中あわせの場所にあって、東支那海に向かってL字状に開いています(辺野古は太平洋側)。L字の角の部分が名護町の海岸、砂浜です。海岸から沖の方(南西方)を見て左側が恩納村の海岸線、右手が本部(もとぶ)半島の海岸線、沖合は東支那海に続きます。
イルカ狩りは、名護の沖合にイルカが現われることで始まります。漁師か誰か、目ざとい者が沖合にイルカの群れがいるのを見つけて、「ヒトドーイ(イルカだぞ!)」と騒ぎぎたてることで祭りが始まります。地元の浜にいるサバニ、小型の漁船などは総動員。漁師はもちろん、漁師でない者も文字どおり押っ取り刀で駆けつけて、イルカの追い込み漁に参加します。小舟はイルカの群れの背後(沖側)や側面に回り込んで、櫂や竹竿で海面を叩いて、イルカの群れが名護の海岸に向かうように追い込みます。
私が若造のころのある日、イルカが名護の浜に寄った、という新聞ニュースを見て、日ごろから不思議に思っていたことを職場の先輩に尋ねました。追い手の小舟がいるとは言え、まだ海岸から離れている広い湾口では逃げようと思えば横にでも後ろにでも、自由自在に逃げられるではないのか、最初から逃げ道はこれしかないと決めたかのように名護の砂浜に向かうというのは何故か。イルカは利口だと言われているがそれほどでもないようですね。大先輩の解説は次のとおり、かなり説得力があり、私は今でもそれが正解であろうと思っています。
沖合にいるイルカから名護町の方向を見ると左手は本部半島の山地、右手も山地で標高が高い。名護の市街地の部分だけが標高が低く、水面に浮かぶイルカの眼にはその部分が‘切れている(海峡になっている)‘ように見えるそうです。イルカは追われても追われなくても、海峡を通りぬけるつもりで名護の町を目指して泳ぐということです。しかし近づいてみたら陸地が現われて、潜って逃げようにも海はすでに浅くなっていて潜れず、追い手の小舟も密集してきて、右からも左からも銛が飛んでくる。包丁を持った人間もとびかかってきて、一巻のおわり、というわけです。
「寄りもの」という言葉があります。人間が能動的に動いて(舟で沖に出たりして)獲物を手に入れるということではなく、魚群あるいはクジラなどが浜に寄せてきて浜辺の住民を喜ばせる。向こうから勝手に寄ってきて近隣住民の糧となる。日本人は古来、寄り物に神の意思を感じてありがたく頂いてきました。名護のイルカもその一種でしょう。浜に寄ってきたものは特定の誰かの所有になるものではない。突然降ってきた天の恵みは皆で分け合うということで、追い込み漁に参加した者も浜で見物した者も適当にお土産が分配されました。しかし、小さくても体長2,3メートル、大きいのは5,6メートルもあるイルカが一度に数十頭も獲れますから、獲物すべてが分配されたということではなかったようです。その日の午後はイルカ肉の入ったタライを頭に乗っけた行商のおばさんたちが、「ヒトコーミソーレ」と声をかけながら町の住宅地を歩いていたそうです。コーミソーレは「買って下さい」ということですから「ヒトはいらんかね」の意味になります。「ヒト」は人間ではなく、イルカのことです。
名護の浜で捕獲されたイルカ肉を一度だけ食べる機会がありました。沖縄島に20年近く住んでいて、イルカ肉(クジラも含めて)料理にありついたのは、あとにも先にもその1回きりです。まだ食べ盛りの高校生で、目の前に出てきた食べ物は何でもおいしく食べる年ごろですから、ほんとにおいしく頂きました。ただ、その時は食べることに注力して調理法などには関心がありません。覚えているのは「みそ味」の煮込みであったことだけです。ニンニクの葉やショウガなどを使ったみそ和えであったと思います。
現在、沖縄でイルカ(クジラ)料理に出会うことはまず考えられません。ものの本によると日本でイルカの獲れる地方のイルカ料理(郷土料理)は実に多種多様、読んでいてよだれを抑えるのに苦労するほどですが、わが沖縄は観光業者むけのホエールワッチングはありながら、スーパーマーケットにも魚屋さんにもイルカ(クジラ)のひとかけらも置いてありません。郷土料理と言えば、豚肉と豆腐をつかったゴーヤーチャンプルーくらいのものでしょう。
名護のイルカ漁も自然消滅したようで覚えているのはお年寄りだけです。もともと、文化というほどのものでもなかったのでしょう。(完)
関連資料
Copyright (c) 1997-2020, Japan Sulawesi Net, All Rights Reserved. |