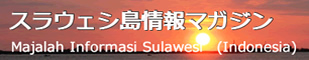 総目次 総目次 |
スラウェシの寛大な海:祖父からの贈り物(1)
山崎 けい子

1.はじめに
夕刻、太陽が西の海へ向かい始める。スラウェシの夕陽は、空を染め強い存在感を示し、燃えながら海に沈んでいく。沈む瞬間ずしりという音が心に響く。そして、スラウェシの寛大な海は、穏やかにすべてを収束させていく。
インドネシア・スラウェシ島は現在の日本人にはなじみの薄いところでもあろうが、観光地として有名なバリ島よりはるかに大きな、アルファベットのKの字の頭の部分をつぶしたような形の島だ。日本からの直行便はなく、ジャワ島ジャカルタ、バリ島デンパサ―ル、あるいはシンガポールから乗り継いでいく(2004年現在)。
しかし、20世紀前半、スラウェシがまだオランダ領セレベス島と呼ばれていた頃、時代の波に乗ろうという血気盛んな日本人にとって、そこは南方貿易の夢の地であったようだ。やがて、日本との交易も進み、セレベス島の最北端にあるメナド(現マナド)はインドネシアの玄関口、海路で日本に一番近い港として栄え、日本人も多く住むようになっていった。日本語の「港(みなと)」が語源であるとも言われている。またメナドはキリスト教の広まった所としても有名だ。
2004年8月、我が家族(母・姉・私)は、そのスラウェシ島へ、思ってもみない旅行をした。それはまるで神様に仕組まれたように始まり、怒涛のような勢いでスラウェシに向かった。なぜ我が家族が呼び寄せられたのか。そこには、世紀を超えた我が祖父の想いがあった。祖父、山崎軍太の熱き想いは、青年、壮年期を通じて南方へ注がれ、世紀を超えて私たちを彼の地へ誘った。祖父のはかりごと、いや、素敵な贈り物。抗いがたい、温かな摩訶不思議なものであった。ありがとう。スラウェシ島。そして、おじいちゃん。
この旅行を思い出して文章にしているのは2006年から2007年にかけてである。あまりにびっくりするような出来事だったので暫くの間は何が起こったのかよく分からなかった。時を待たねば言葉にならないということがある。
2.軍太の人生
まず、この話の源、山崎軍太の人生を紹介しなければならないだろう。孫の私も多くを知るわけではないが、祖父が他界してから20年以上、風化しそうな資料を集めて祖父の人生を辿ってみる。
話は、明治時代にまで遡る。1894年(明治27年)、軍太誕生。学生時代の軍太は背こそ低いけれど、剣道の主将で鳴らした硬派であった。血気盛んで何かを成し遂げてやろうという熱き想いを抱いた22、3の青年が、卒業後、生まれ育った九州の地から南方の島に憧れ、南方事業の会社に夢の就職先を決めたのは、1917年(大正6年)のことであった。

就職してほどなくインドネシア・セレベス(現在のスラウェシ)への派遣が決まった軍太は、急遽お見合いで花嫁を決めた。美智子がその人である。美智子の妹の方が色が白く美人であったらしいが、軍太は弱々しく食の細い妹よりも、出された食事を美味しそうに食べる健康的な美智子を選んだという。南方の楽園と言ってもまだまだ未開とも言える島へ連れて行く花嫁なのだから当然かもしれない。祖母の名誉のために付け加えておくが、美智子がけっして美人でなかったと言っているわけではないが、それより才女という言葉に近い人だ。東京の女子英学塾(現津田塾大学)に通っていたのを途中でやめての嫁入りだった。せっかく入った学校にかなりの未練があったようだが、しかし、身内のひいき目ではあるが、祖父は、背こそ低いが所謂イケメンタイプだったので、祖母もまあ救われたのではないだろうか。(写真(右上)軍太夫婦の新婚の頃)
そして、二人で新婚の生活を送ったのが、セレベス島のメナド(現スラウェシ島マナド)である。オランダの影響を受け、独特のムードがあったと言う。慣れぬ土地ではじめての苦労も多かったようだが、新婚当時は、セレベス島のみならず、ジャワ島の名所旧跡にまで足を伸ばし楽しそうな旅をしている写真も残っている。
軍太自身、「メナド支店に腰を落ち付けて10年間、貿易、運輸、拓殖、水産、鉱業、油脂と、何でもござれのモウレツ社員。(山崎軍太「わたしの自叙伝」『南興』58号1979年)」と当時を振り返っている。メナドから少し奥地に入ったところに自分のコーヒー園を持つなど、彼の地だから出来ることも思う存分していたようだ。そして、子供を授かる、メナド支店長になる、日本人会会長を務めるなど、軍太は少しずつ人生の階段を上って行く。
 (我が子を抱く美智子)
(我が子を抱く美智子)
 (モダヤ山崎コーヒー園)
(モダヤ山崎コーヒー園)
その後いったんメナドを引き上げ、軍太は日本国内の勤務のため数年日本で暮らすが、1934年(昭和9年)頃、望まれて軍太は南方へとまた向かう。この時は、メナド生まれの上の二人の女の子を教育のため日本に預け、美智子と末息子だけが同行し、メナドに再び居を構えている。
1935年元旦からの美智子の日記が残っている。多くの、日本人、現地の人、外国人との交流が記されてもいるが、記録として面白いところだけをまとめてみよう。
「昭和十年一月一日 1935 除夜の鐘ならぬ爆竹の音打上げる花火に昭和九年のとばりは静に下され・・・午前中から坊やが熱を出し夜通し水でひやす。・・・九度一分まで下がり、二日の朝には平熱」とあり、元旦から末息子の健康の心配をしている。しかし、例年の通り日本人会が開かれ、24、5名の人が集まっている。献立は鮎、数の子、黒豆、サラダ、コロッケ、サテ、バビケチャップ、煮しめ、魚の丸あげ、塩鮭、栗きんとん・・・など多すぎたようだと書いているほど、盛りだくさんだ。
「一月二十二日 一昨日の夜からまた坊や熱を出す。・・・やっぱりマラリアらしいので夜にはキニーネをのませた所が夜九時頃に熱にうなされた風でうわ言の様なのをいい出したのでびっくりして・・・」末息子はマラリアに苦しめられておりその不安がこの後も綴られている。しかし何とか持ち直したようで、末息子の小学校入学のため、1935年の3月30日に、3人はメナドから日本へ向けた船に乗っている。
4月1日、ダバオに着き下船見物。3日パラオ入港。会社の方の歓迎。
ここに気になる記述がある。「しきりに山崎をパラオにといわれるよしぶるぶるする」とある。色々な記録が一致せず不明な点も多いが、軍太はこの時はまだパラオ島を管轄してはいないようだ。美智子はパラオなら軍太の単身赴任になると嫌がっている。
4日パラオ出航。6日ヤップ。7日テニアン。8日テニアンから小舟でサイパン見物とある。それぞれの寄港地で、会社関係と思しき知人、テニアン支店長などたくさんの人に会っている記述には驚く。軍太の仕事はこのルートの貿易であったのだろうし、また何度も行き来するうちにつながりも出来ていたのだろう。
この後、4月10日に記述があり「いよいよ南洋とおさらばの日が来る。本朝からめっきり涼しくなる。子供達に会うのも二、三日の後」とある。当時メナドから日本まで2週間程の船旅だったようだ。
この旅は軍太にとっては一時帰国だったのだろうが、美智子はしばらく日本に滞在している。そして、翌1936年8月、3人の子供達を日本に残したまま、再びメナドでの生活を始め、「おいてきた子供隊への赦免の積もりで心を引き締め習字と英語と料理と洋裁」に磨きをかけている。しかし、日本に残して来た子供達のことをしきりに気にかけ、手紙(船便)が届くのを心待ちにしている。日本丸、ジョホール丸、マカッサル丸などの船の名前が出てくる。あまり来ないようなら、電報を打つというのが当時の状況だったようだ。
1936年10月27日の日記には「本社から主人にパラオ支店長の交渉の手紙。」「兼任とか言うものの・・・パラオが主でこちらが従らしい」とある。本当にパラオ支店長になったのは翌年のことのようだ。美智子は、子供が病気で入院したこともあり1937年の正月は日本で迎えている。以後、美智子の南方での生活は記録されていない。(戦時中の記録もない。)
これ以降、軍太は単身、彼の地で過し、南洋群島総括支店長としてパラオを中心に充実した仕事をしていたようだ。1941年には、軍太は現地駐在の取締役にもなる。この時点で、最初の赴任から20年余、南方を愛しマレー語が堪能な軍太は、現地の事業にこそ水を得た魚のように力を発揮できる人材になっていたのではないだろうか。
しかし、時代は戦争に突入して行く。軍太は何を思ったのだろうか。40も半ばをこえた歳で、民間人として海軍経済顧問に徴用され南方攻略に同行をする。フィリピン島ダパオを経て、メナド上陸。侵攻のさなか、堪能なマレー語と今まで培ったつながりを生かし、現地の民間人に通じ安定をはかり、食料調達などを行ったようだ。次いで、マカッサル上陸。そして、我が祖父は第二次大戦中、セレベス島マカッサル市の特別市長を務めた(1942年4月から終戦まで)。マカッサルには非常に激しい戦火は少なかったらしく、市長として、立派な市庁舎で仕事をし現地の人と交わることも出来たようだ。
 (市長を務めた頃か、それ前後の軍太)
(市長を務めた頃か、それ前後の軍太)
 (前列左から2番目軍太、3番目森中将)
(前列左から2番目軍太、3番目森中将)
1945年、敗戦。軍太は東京に戻ってくるも、BC級戦犯として巣鴨に収容される。オランダ船でまたマカッサルに戻されマカッサル刑務所に入る。「刑務所はコンクリートの床にアンペラを敷くのみの酷遇、身にはサル又のみの裸一貫、独房には高所に小窓一つ、トイレは空缶のみ。夕方になれば小窓からマラリヤ蚊の襲撃に遭う、というまったく酷なものであった(山崎軍太「剣道の賜」『南興』58号)」。そして、オランダによる裁判を受けた。セレベス島の他の地域で同じく日本人特別市長であった方々の中には、死刑判決を受けた方もいると聞く。しかし、本当にありがたいことに、戦火がそれほどひどくなかったマカッサルは市民感情があまり悪くなかったらしい。「ミスターは、そんなひどいことはしなかった」と、軍太のために証言する現地の方もいたという。また、軍太は民間人で軍籍にはなかったし、マカッサルの日本軍中将(司令官)がすべての責任は私にあると敢えて言明されたということもあり(この森中将を軍太は生涯尊敬していた)、晴れて、軍太は不起訴で放免となる。
不起訴が決まるまでの間に美智子に書いて出した葉書が残っている。「風邪ひとつ引かずに頑張っています。旧知の人達と一共に談笑の夕を過しつつ、静かに祈りの生活を繰返しています。」「聖書を読むのとお祈りは私の生活の糧です。」などという文章もある。軍太はキリスト教徒ではなかったが、これを読む限りでは、神を信じる気持ちは強かったようで神の与えた試練をいかに受け入れるかを考えている。
また晩年、軍太はこの頃を思い出し以下のようにも綴っている。「かかる苦汁を呑みながら風邪一つ引かず帰還したのは精神力や体力のお蔭で、剣道修業の賜に外ならぬ。(山崎軍太「剣道の賜」『南興』58号)」いかに精神と体を鍛えるかが肝要だと思っていたようだ。
軍太は日本へ戻ってはきたが、公職追放の身となっており、表の舞台で活躍することは難しくなっていた。闇の商売で一儲けしたこともあるようだが、その後の軍太はそれまでの華やかな半生に比べれば、地味な人生を送ることになる。そして他界するまで、戦争前、戦争中のことを身近な者に多く語らなかった。祖母も語らなかった。少なくとも孫の私は何も聞いたことがない。今回祖父のことを調べ出して、文章になったものがあるのを初めて知った。祖父の想いを初めて知った。あの時代の人はそうなのだろうか。それとも、口に出して語るには重すぎることだったのだろうか。
一度、私の小学校の宿題で「おじいちゃんの仕事」というのを調べたことがあった。祖父が何をしていたのかと母に尋ねて、インドネシアのセレベス島で市長をしていたことがあるというのを初めて聞いた。
「嘘だ~!なんで日本人なのにそんなこと出来るの?」
「戦争中にやっていたのよ。」
当時、小学生の私はよく分からずに、祖父に電話した。
「セレベス島で市長やってたの?」
「ああ、そうね…。マカッサルで市長やってたんだよ。」
「ふーん。どんなことしてたの?」
と、聞いたが、祖父はあまりたいしたことを語らなかったのを覚えている。だから私もたいしたことだとは思わなかった。
母に言わせれば、祖父は「豪放磊落」という言葉がぴったりの人だったと言う。母は祖父に怒られたことがないと言う。明るく、にぎやかなことが好きで、大きなことが好き。人の好き嫌いはあったが、自分がこれと思った人にはとことん誠を尽くしたとも言う。
孫の私にとっては、声の大きな明るいおじいちゃん、である。孫に「○○ちゃんや」と言いながらほっぺにキスをするのが大好きな人であった。
しかし確かに、風変わりな祖父母であった。明治生まれのおじいちゃんとおばあちゃんが洋風の部屋の大きなベッドで寝ていたし、家には不思議な置物、飾り物がたくさん飾られていた。(今それらを手に取ってみると、確かにインドネシアのものばかりである。)人に聞かれたくないことがあると、二人で何だか訳の分からない言葉(マレー語)でぺらぺら話していた。
祖父はあと2か月で90歳というところまで存命であった。祖母も同じように長命であった。二人は本当に仲良く寄り添って老後を過ごした。
1984年、祖父を最後に病院に見舞った時、89歳の祖父は眼鏡をかけて熱心に日経新聞の株欄を見ていた。
「おじいちゃん、まだ株やるの?」
私が聞くと
「うん。まだやるよ。人間、やるぞっていう気持ちが消えちゃだめだよ。僕あ、まだまだやりますよ。」
と、言っていた。私は驚きの目で祖父を見つめた。体力は明らかに衰えてベッドに横たわっていたが、その精神は変わらずに力強かった。私は祖父の生きる力に感動し、励まされた。
3.子供はセレベス島生まれだが
そんな経緯で我が母はセレベス島生まれである。祖父母の3人の子供はみなメナドで幼少の時を過している。しかし、母は2歳か3歳の頃に日本へ戻ってきている。母にはメナドの記憶はほとんどなく、ましてやマカッサルには行ったこともなかった。末子の叔父も、マラリアでひどくやられて当時の記憶はぼんやりしていると言う。メナドでは教会の裏の白い大きな家に住んでいたということだけがおぼろげにあるだけだった。母の3歳違いの姉はメナドを少し記憶していたようで、大きな庭に鹿がいて、追いかけ回して遊んでいたとか言っていたようだ。
そんな記憶の薄いセレベス島であるが、祖父がマカッサル市長であったことは、母には大切な意味を持っていた。自分の生まれた地を祖父と共にもう一度踏みたい、祖父の輝いていた時代を一緒に振り返りたいという思いがあった。セレベス島という土地と、自分とのつながりを確かに手にとってみたかったのだろう。しかし、残念ながら祖父の存命中は実現しなかった。祖父は戦後インドネシアを確かに一度は訪れており、ジャカルタで撮ったと思しき写真が残っているが、セレベスまでは行かなかったのではないかと思われる。母は今でも祖父と共にセレベスに行けたとしたら祖父はいったいどんなことを語ったのだろうか、聞いてみたかったと悔やんでいる。
祖父の他界後、セレベスはさらに遠くなった。
ジャカルタならまだしも、セレベスとはどこにあるのだろう?それに今はスラウェシ。メナドではなくてマナド。マカッサルでもなくてウジュンパンダン(最近再度マカッサルに呼び名が戻った)。いやはや、そこへはどうやって行くのだろう?
母には申し訳ないが、メナドに行ってみたいという母の小さな声を家族は誰も本気で聞こうとしていなかった。母自身も自分だけではどうしようもないと思っていた。夢のまた夢。しかしながら、不思議なことに2003年、まるで機が熟したように色々な動きが次第に重なり合い、スラウェシへと誘われていく。
4.スラウェシへいざなわれ
現在、祖父母の子供で生き残っているのは母だけである。しかし、まだ母の弟(私の叔父)が存命であった2003年の秋、一冊の本が叔父のところに届いた(著者からの献本)。病に苦しんでいた叔父はそれをそのまま母に渡した。永江勝朗氏著による「身近にあった戦場」(『文集小さな炎』第17号2003年)の中には、セレベスで出会った当時の軍太のことが記述されていた。
それと同時期、マカッサル市立博物館の館長が、歴代の市長の写真やプロフィールを集めて展示しようとしていた。長い時を経て、不起訴放免となった事実を認め、歴代市長の中に軍太の名を連ね名誉を回復させようとしていた。当時の在マカッサル総領事(渡邉奉勝氏)がそれを手助けし、様々なつてをたどって軍太の写真やプロフィールを探していた。そして、前述の「身近にあった戦場」で軍太の記事を探しあて、軍太の会社関係の知人より写真を入手し、マカッサル市立博物館に軍太の写真が飾られる運びになっていた。
実は、我が家族はそのことをまったく知らずにいた。だが、我が家でも永江氏のことが話題になり、母は再びセレベスへの想いを強く示していた。
ここで、兄嫁が活躍する。義姉は今まで聞き捨てられて来た母のメナドへ行きたいという願いをかなえようと本気で考えた。2004年3月、義姉はネットでスラウェシを検索し、スラウェシに関するHP「スラウェシ島情報マガジン」(脇田清之氏運営)に行き着いた。そして、マカッサル市立博物館に軍太の写真が飾られたニュースが掲載されていることに初めて気がつく。ホームページでみる祖父の写真は非常なインパクトがあった。
マカッサルで、祖父の写真が!?非常な驚きであった。しかし、残念ながら、叔父(祖父の長男)は、祖父の写真が博物館展示されたニュースを聞くか聞かずのところで逝ってしまった。
義姉は、HP「スラウェシ島情報マガジン」で軍太の記事を発見するや、持ち前の行動力で即座に脇田氏にメールを送った。そこから永江氏、渡邊氏を紹介され、丁寧なやり取りの中での優しいつながりが始まっていった。さらに、スラウェシ情報に詳しい松井和久氏をはじめとするたくさんの方々へ「スラウェシ・ネットワーク」は広がっていった。
そんな名前のネットワークが存在するわけではないが、スラウェシを愛し、関わる人たちの自然発生的なつながりがあり、私はそれをそう呼びたいと思う。ホームページ、Eメール、という現代のツールにより、インドネシアとは遠くにあっても簡単につながれた。だんだん母もその気になっていき、母の末子である私もこのスラウェシ・ネットワークにはまっていった。私はコンピュータが自由に使える環境にあったので、このネットワークへの連絡窓口として適していたのだろう。
本当のところ、この旅行は簡単なことではなかった。母は80という高齢である。デング熱にでもかかったらという心配から始まり、現実的に、例えば日本からではマカッサルのホテルに予約を取ることもできなかった。旅行社がデータを持っていないというのだ。
まず、母を強力サポートするために、姉(長女)と私(次女)が同行することにした(兄(長男)夫婦は都合により断念)。スラウェシ・ネットワークを通じて知り合った方々が、実際にスラウェシに行くことが方法さえ分かればそれほど難しくないこと、また彼の地の魅力は言葉で言い表せないほどであることを、メール等で異口同音に語り、励ましてくださった。この方たちの並々ならぬサポートを受け、本当にスラウェシ島へ母を連れて行くのだという覚悟が次第に出来ていった。いや、自分たちの目で祖父母の辿ったものを確かめることが使命のようにも思えてきた。 加えて、軍太が当時ミナハサの偉い方から贈られた刀をマナドの博物館へ寄贈する、という母の思い付きによるおまけまでつけることになった。

(刀の鞘に施された象牙の彫り物)

実は母は当初、これは刀ではなくただの細長い飾り物だと思っていた。晩年祖父が伊豆へ隠居のため引っ越す際、「えらい方から贈り物としてもらったものだ。大切にしてくれ」と母に手渡したと言うのだが、それだけで何も詳しいことは聞いていなかった。長さは1メートルを超え、鞘には象牙などで装飾がほどこされている。男女の営みのおおらかな彫り物があり、聖なる雰囲気もある。象徴的なものであるので「スラウェシ島との交友の証し」としてお返ししたらという思いつきだったのだ。時を経て傷みも多少出てきており、ふるさとに戻って修復の機会でも得られれば、それが一番良いことのように思えた。
しかし、お返しするのだからとつぶさに調べてみたら、なんとそれは飾り物ではなく、錆び付いているとはいえ、刀であることが分かった。ここまで気がつかずにいた我々も救いがたいが、しかし、これには本当に驚き、困った。どうやって刀を寄贈などできるのだろう。さまざまな手続きが不可能に思えた。いったんは、思いつきは萎みかけた。
しかし、後になって考えれば分からぬもので、この母の無茶な思い付きこそがいろいろな方とさらにつながっていく原動力となった。わずかな可能性を探る中で、北スラウェシ州立博物館に照会しミナハサ族のものであろうとの回答を得たり、偶然マカッサル市立博物館長が来日、我が家で刀を鑑定しこれはまず本物だろうというお墨付きが出たり、インドネシア大使館関係者にご厚情を得たりなど、数え切れないほどたくさんの方々の手助けがあった。お膳立てをしてくださったのは、もちろん前述のスラウェシ・ネットワークの方々だった。途中何度も挫折しかけたのだが、そのたびに、不思議と道が開けた。関係の方々にどんなに感謝をしても仕切れない。
しかし、なぜ見ず知らずの私たちにそんなにたくさんの助けの手が伸びたのだろう。母自身もいくつかの場所に足を運んだ。姉はそれこそ東奔西走、母と離れて地方に住む私もネットで多数のメールを毎日飛ばし続けた。このテクノロジーがなければ今回の成功はあり得なかった。しかし、それだけではない。人の想いがつながなければテクノロジーも機能しない。祖父軍太の想いが後押し、人の想いをつなげたとしか思えない。軍太がスラウェシで過ごした日々や、マカッサル市長を務めたということが、それほど重い事実であったのだと改めて思う。その歴史的事実に興味を覚え、手助けを申し出てくださった方々がいらした。それこそが、祖父からの贈り物であった。
誤植訂正:2007-10-19
スマホ対応:2020-5-14
Copyright (c) 1997-2020, Japan Sulawesi Net, All Rights Reserved. |