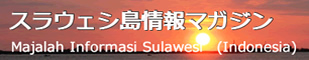 総目次 総目次 |
セレベス新聞時代を顧みて(1)
Retrospeksi masa redaksi "Harian Pewarta Selebes"
di Makassar selama 1943-45 (1)
黒崎 久 Kurosaki Hisashi (1919.2.25 - 2020.4.3)
毎日新聞社に入社して間もない、昭和18年11月に、丸の内の東京会館で大東亜新聞会議が催された。この会議は日本の軍政下にあった諸地域で発行されていた現地語新聞の編集長クラスの記者を招き、日本が唱えた大東亜共栄圈づくりに協力させ、現地人の戦争協力意欲を高めようとするねらいから開かれたもので、東条英樹首相以下陸海軍の報道関係参謀らが出席した。
太平洋戦争は昭和17年6月5日のミッドウェー海戦で日本海軍が大敗してから戦況がとみに不利になり、士気を鼓舞するため軍政下にあった諸地域で日本語新聞と現地語新聞を発行する必要にせまられ、各新聞社にそれが委託された。地域別に見ると、朝日新聞社は旧蘭印のジャワ島とボルネオ島(現在はカリマンタン島と名づけられている)、毎日新聞社はフィリピン全土と旧蘭印のセレベス島(現スラウェシ島)、読売新聞社がビルマ(現ミャンマー)と旧蘭印のセラム(ハルマヘラ諸島の一つ)、同盟通信(現共同通信)と主要地方新聞は共同で旧蘭印のスマトラ島と旧イギリス植民地のマレー半島とシンガポール(当時は昭南島と名づけられていた)というように分担してそれぞれ邦字紙(日本語紙)と現地語紙の発行を 委託された。

わたしは昭和18年12月15日付でセレベス新聞へ出向を命じられた。セレベス新聞は本社がマカッサルに、支社がメナドにあった。マカッサル本社では開戦一周年に当たる昭和17年12月8日から邦字紙セレベス新聞と馬来語(インドネシア語)紙のプワルタ・セレペスの発行を開始していた。メナドのプワルタ・セレベス新聞はマカッサルより遅れて昭和18年4月29日(天長節に合わせたか)から発行された。マカッサルで発行でされた邦字紙の部数は当初は三千部、プワルターセレベスは一万部であったが、最盛時には邦字紙八千部、プワルタ・セレベスが三万部に達した。(写真上:セレベス新聞創刊日の記念写真)
わたしはセレベス新聞出向を命じられるとすぐ家族に別れを告げるため帰郷した。セレベス新聞社への出向は兵士の出征ともいうべきもので、ムケの綱川家の正一郎さん、隣りの加藤忠弥さん、北隣りの綱川近三郎さんも来て送ってくれた。その日、父は息子の旅立ちとあって、わたしと餅つきをしたが、父は大きな杵、わたしは小さな杵でついた。六十七歳の父の餅つきぶりは元気そのもので、わたしは圧倒され気味であった。いよいよ別れを告げて実家を去ったが、わたしの姿が白石を過ぎて見えなくなったころ、囲炉裏を囲んで座っていた父は突然倒れたという。酒好きの父であったから脳卒中であったろう。わたしはそんなことはつゆ知らず、板橋警察署わきの平三郎叔父の家に着いたところへ、父の異変を知らせに正一郎さんがかけつけてくれた。わたしはとるものもとりあえず実家にかけ戻ったが、父はすでに意識がなく、祖母が父の枕元に座って看病している姿が痛々しかった。仕方なくわたしは再び別れを告げ東京に引き返すよりほかにすべはなかった。父と祖母を見たのはこれが最後、今生の別れとなった。
大東亜新聞会議にはマカッサルのプワルタ・セレベスの事実上の編集長であったマナイ・ソフィアン記者とメナド支社のパントウ記者が出席した。わたしはこの機会にもっぱらマナイ・ソフィアン記者につきそい、東京の各所を案内したりした。 たしか12月12日だったと思う。わたしはマナイ・ソフィアンと同行する形でマカッサルへ向けて出発した。その前夜は帝国ホテルに宿泊した。わたしたちは羽田空港から毎日新聞社の社機で赴任したが、ほかにマカッサルのセレベス新聞へ出向を命じられた山下丈二とマニラ新聞へ出向する某記者も同乗した。社機といっても海軍から払い下げられた双発機で、人員を輸送するのが目的ではなく、荷物輸送が主目的であったから、わたしたちは貨物の間に身をちぢめて寒さに身ぶるいした。 上海、台湾の高雄、マニラ、メナドでそれぞれ一泊、四日がかりでマカッサルに着いた。途中高雄で買い求めたバナナを機中で食べ、その皮を飛行機の窓から投げ捨てられるという、今では信じられないほどの飛行機であった。そのころ戦況とみにふるわず、マカッサルは大東亜新聞会議が開かれたころ、アメリカのB26爆撃機の爆撃に見舞われ始めていた。飛行機のパイロットも毎日新聞社員で、敵機が飛来してはたいへんだから、よく見張りしてくれなどと言われた。しかし、そんな恐れもなく、無事メナド上空にさしかかった時は白いヤシ林が眼下に見え、「ああ、これがインドネシアか」と胸がおどる思いがした。

セレベス新聞に出向した毎日新聞社員は名簿によると六十九人に達していた。うち馬来語(インドネシア語)日刊紙プワルタ・セレペス関係者はわたしを含めて四人であったが、わたしはセレベス新聞社員では最年少者だった。一方メナド支社には二十人が出向していた。マカッサル本社のプワルタ・セレペスの現地人記者は最盛時にはタイピストを含め二十人に達した。マカッサル族、ブキス族、セレベス島北部のミナハサ族とゴロンタロ族、ジャワ族、スマトラ島生まれなど雑多な構成であった。わたしは着任早々これら現地人記者に自己紹介したとき、薗田先生から教わったアラビア文字で名を書いて見せたので、彼らはびっくりした。日本人がなぜアラビア文字が書けるのだろうと不思議に思ったにちがいない。わたしはアラビア文字が役立つたかと、いささか得意な気分になった。
わたしの初仕事は大東亜新聞会議に出席したマナイ・ソフィアン記者がプワルタ・セレペス紙に連載した日本訪問記を翻訳してセレベス新聞に載せたことである。わたしが日本語で記事を書いたのはこれが最初であった。編集局の宮沢大元編集部長から「よく翻訳してあったな」とおほめの言葉をいただいたのには恐れいるとともに嬉しくもあった(写真上:セレベス新聞 昭和19年2月6日号 1面記事 マナイ・ソピアン手記(中))。
わたしが着任したとき、プワルタ・セレペスには編集長の近藤三郎氏は別として、わたしと同年輩の花岡泰隆君のほかに現地採用で社員名簿には載らなかった大阪外語卒業の植村某と藤田某の二人がいた。翌年春にわたしより五歳年長の木村操さんが着任して間もなく、この二人はなぜかしらやめてしまった。花岡君のお父さんはジャワで銀行業関係に勤めていた俳人で、花岡君と彼の兄の泰次さんはジャワ生まれで両人ともインドネシア語を解し、戦後兄弟で「インドネシア民話集」という訳編本を出版した。木村さんは温厚篤実な人柄で、お姉さんがジャワでジャワ日報の社長をしておられた斎藤正雄氏に嫁いでいた関係からかして、斎藤氏にすすめられてジャワに渡り、初めオランダ語、ついでインドネシア語を数年間勉強してインドネシア語にはとくに精通し、戦後インドネシアを代表する作家のタクディル・アリシャバナ、モフタル・ルビス、アルメイン・パネなどの著書を翻訳出版し好評を博した。木村さんは初めセレベス新聞社員と同宿していたが、その宿舎が爆撃でこわされたので、プワルタ・セレペスの記者をしていたハルソノ女史の家に寄宿し終戦を迎えた。爆撃といえば、わたしが着任したころから烈しくなり、日夜を問わずほとんど毎日のようにアメリカ機に爆撃された。昼間の爆撃では飛行機が見えるからよかったものの、夜間爆撃では飛行方向が分からないから、空襲警報が鳴るたびに防空壕にとびこまなければならなかった。アメリカ爆撃機の主目標はマカッサルではなく、石油精製所があったボルネオのバリクパパンとタラカンで、マカッサルはそのコース上にあるため行き帰りの途中に爆弾を投下したものらしい。
わたしは着任したものの、適当な宿舎がなく、しばらくの間マカッサル海峡の海辺に近い大和ホテルに宿泊した。のち近藤三郎編集長のはからいでマナイ・ソフィアン記者のお宅に寄宿させてもらった。マナイ・ソフィアンは民族主義者の熱血漢で、そのころすでに民族運動の指導者になっていた。彼が金婚式を記念して出版した著書によると、或る日突然一人の日本人が訪ねて来て、インドネシア語新聞を創刊するから協力してほしいと要請された。その日本人こそ近藤三郎編集長であった。近藤編集長は前記の斉藤正雄氏の世話になった人らしく、インドネシア語の達人でインドネシア人の民族主義に共鳴し、マナイ・ソフィアンとともにマカッサル在住の有識者と交流し、のち現地人の州会議員を選出するに当たっては、この両者がその人選に当たったらしい。マナイ・ソフィアンは戦後オランダ側に捕らえられたが脱獄し、ジャワに渡り、初代大統領のスカルノの信頼を得て、スカルノが組織したインドネシア国民党の書記長をつとめ、国会議員に選ばれたりし、のち国連大使を経て最後は旧ソビエト駐在大使に任ぜられた。スカルノが失脚した二年後に官を辞し、フリーライターとなって活躍した。わたしがマナイ・ソフィアンの家に厄介になっていたころ、まだよちよち歩きだった息子のソファン・ソフィアンは長じて映画俳優・映画監督となり、彼が主演した映画がマニラで開かれたアジア映画祭でグランプリを受賞した。彼も父同様国会議員になり、かたわら芸能関係団体の会長をしたりし、現在は国会議員であると同時に国家の最高議決機関である国民協議会の与党闘争民主党派の会長に就いている(2001年現在)。
ところで、わたしの主な仕事は同盟通信(現共同通信)から配信されるニュースやセレベス新聞に載り、現地人に知らしめるがよいと思われる記事をインドネシア語に翻訳することであった。かたわら、現地人で日本企業や官庁に勤める若人たちを夕方小学校に集め、日本語の初歩を教えたり、しばらくラジオで日本語講座を担当したりした。しかし、一般家庭でラジオを備えることが禁じられていて、街の辻々にラジオ塔のようなものを設けるだけだったから、日本語講座を聞く物好きもほとんどいなかったようである。親しいインドネシア人記者のハジャラティから「あなたの日本語講座を聞いているのは蚊だけですよ」と冗談半分にひやかされたものである。わたしの日本語は栃木なまりでもあるからもっともな話である。
関連資料
注:著者のご了解を頂き「八十年を顧みて」(平成13年10月25日発行)の一部をそのまま転載させて頂きました。(編集部)
毎日新聞OB交流サイトに下記の記事がありました。
「101歳で亡くなった「セレベス新聞」最年少記者・黒崎久さん」
https://www.maiyukai.com/memorial#20200513