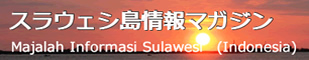 総目次 総目次 |
セレベス新聞時代を顧みて(3)
Retrospeksi masa redaksi "Harian Pewarta Selebes"
di Makassar selama 1943-45 (3)
黒崎 久 Kurosaki Hisashi
戦況はますます不利になり、いつ敵が進攻してくるかわからない事態になったので、セレベス新聞はいざという時に備えて、新聞印刷用の機器や活字の一部を奥地のトラジャ地方に疎開させ、新聞発行を続ける準備をせざるを得なかった。
大本営発表を翻訳するわたしどもはやるせなかったが、かくすわけにはいかなかった。そのころになると、日本が旗印としていて、たかだかと喧伝し、新聞でもしきりに書き立てた「大東亜共栄圏」という標語も空疎でむなしくなり、新聞に載ることもなくなってしまった。
終戦直前、原子爆弾が投下された時は、プワルタ・セレベスに新型爆弾が投下されたという簡単な記事を載せただけだった。それは同盟通信から配信されたニュースがそれだけの簡単なものだったからであろう。いよいよ終戦となったときには困った。現地の住民たちの間にはひそかに短波放送で日本が無条件降伏をした事実を知っていた者もいたようだし、いつまでもかくしておくわけにもいかず、近藤編集長とも図って終戦の記事を載せることにした。ややこしかったのは終戦の詔勅を翻訳することであった。難解な詔勅を全文翻訳するわけにもいかず、わたしとマナ イ・ソフィアンの二人が一室に閉じこもって、ほとんど徹夜で詔勅を抄訳した。これがわたしにとってはプワルタ・セレペスにおける最後の仕事となった。プワルタ・セレペスは8月20日をもって終刊となった。終刊は856号であった。プワルタ・セレベスの発行に携わった期間はそれほど長くなかったが、わたしの人生の中では密度が高かったと思う。
わたしのプワルタ・セレベスにおける仕事はマナイ・ソフィアンと共に始まり、マナイ・ソフィアンと共に終わった。プワルタ・セレベス紙は毎日新聞調査部にマイクロ・フィルムとして保管されているが、終戦直前の新聞は戦況悪化で届かず、最後の仕事となった記事が残されていないのは残念のきわみである。 近藤三郎氏の倉庫にはいざという時に備えて布地類のほかに日本刀や小銃などの武器も保管されていた。連合軍が進駐して来るからには武器保管は危険というわけで、わたしは前記今村君の運転する自動車で、これらの武器を夕日の絶景で知られるマカッサル海に棄てに行かされた。これが最後の最後の仕事となった。
逆戻りするがここらで、プワルタ・セレベスの名目上の編集長で総括的に同紙を統轄した近藤三郎と事実上の編集長であったマナイ・ソフィアンについて触れておきたい。この両者をさしおいてプワルタ・セレベスを語れない。両者の関係は二者一体ともいうべき緊密さで終始した。

近藤三郎は大正元年(1912年)、愛知県幡豆郡豊坂村生まれ。農学校を卒業後、16歳で東京府下上板橋村字小竹(現在練馬区小竹町)の日本力行会の海外学校に学んだ。日本力行会は苦学生救済のために設立されたもので、文京区小石川にあったころ、明治35年には詩人石川啄木が力行会苦学部に学んだという。近藤は昭和6年、南方雄飛を志してジャワに渡り、マランでタマン・シスワに学んだ。
タマン・シスワはオランダ植民政庁に依存しない有名な私立学校で、ジャワの主要都市に設立されていた。近藤は同校で聖書のインドネシア語版でインドネシア語を勉強し、卒業後24歳で前述のジャワ日報、26歳で東印度日報の記者となった。近藤のインドネシア語はインドネシア人も及ばないほどのものであったという。小肥りの小柄な体格で、性格は剛胆。激情、情熱家、勝ち気、親分肌という形容が当てはまる人物であった。風雲急を告げる昭和16年12月1日に帰国し、大東亜戦争(太平洋戦争)勃発の翌年3月に海軍報道班員としてジャワに赴き、ジャカルタに駐在していた海軍武官府の前田精海軍少将の密命をおびて、海軍の軍政治下にあったマカッサルでインドネシア語新聞を発行するため、マカッサルに渡り、同年5月、マナイ・ソフィアン宅を訪れて協力を申し入れた。海軍武官府というのは、インドネシアのうちジャワ島とスマトラ島の陸軍軍政治下の地域と海軍軍政下にあったインドネシアの他地域の間にあって両地域軍政の連絡・調整を図る重要機関であった。資金も潤沢であった。近藤のほか小林哲男と吉住留五郎の二人も、前田武官の命をおびてマカッサルに渡った。小林は近藤と同年輩で、日本大学在学中、二・二六事件に連座したが、山下奉文陸軍大将に助けられて、エジプトのカイロ駐在総領事に預けられ、同地でイスラム教(回教)圏でいちばん古いアズファイサル大学を卒業した。吉住は海軍軍令部と外務省の嘱託として情報工作を任務とした。
つまるところ海軍は小林に回教を通じ、また近藤に新聞を通じ、吉住に情報活動を通じて現地人の宣撫と戦争協力を図ったのである。
小林は回教協会の会長となり、近藤は毎日新聞社に請われて毎日新聞社員としてプワルタ・セレベスの編集長となった。近藤と小林は義兄弟の誓いを行い、日本を中心とするアジア主義、インドネシア民族運動・独立要求支持、キリスト教的人間愛をスローガンとした。近藤は毎日新聞とは距離を置き、セレベス新聞社幹部ともそりが合わなかった。近藤と小林はプワルタ・セレベスをセレベス新聞から独立させ、インドネシア独立のための純然たる政治宣伝機関にする考えを抱くに至った。これには回教協会の機密資金を当てようとしたが、小林がアンボンへ出張の帰りに飛行機が撃墜され、彼の死で実現されなかった。ちなみに海軍武官府の前田精少将は東京外語の速成科でオランダ語を学び、オランダに駐在中、オランダに留学していたインドネシア人と面識を得た。インドネシアが終戦の翌々日、独立宣言をするに当たり、スカルノらを私宅に招き、独立宣言日の払暁、スカルノはそこで自ら独立宣言文を書いた。インドネシアの百科事典に前田精(ただし)の項があるのもむべなるかなである。
マナイ・ソフィアンは1915年生まれのブギス人で、近藤と同じくジョクジヤカルタのタマン・シスワを卒業し、マカッサルで教員をするかたわら、民族運動の指導者として名を知られ、オランダ側に忌まれて追放され、近藤が訪れたころは失業中であったという。近藤と対照的に長身の美男子で、熱血漢であり、スカルノばりの雄弁家である。大東亜新聞会議に出席して帰国後の1944年1月5日から2月10日まで、「日本国を訪問して」を表向きの論題として、南セレベスの27都市を歴訪し、民族運動の重要性を説いて廻った。
近藤に新聞発行の協力を求められた時は即座に返答せず、新聞発行ではセレベスより遙かに進んだジャワに渡り、新聞発行に必要な知識を仕入れ、つてを求めてスカルノに会った。その時スカルノは「いつも独立を念頭におけ」と助言したという。マナイ・ソフィアンはその一言で新聞発行に携わる決意をし、近藤に協力することを誓った。前述のとおり、近藤はインドネシア民族の独立要求に理解を示し、その運動を積極的に支持したから、両者はお互いに胸襟を開き、以後二者一体となってプワルタ・セレベスの発行に当たった。両者はいわばプワルタ・セレベスという独立要求支持メディアの車の両輪となった。
前後するが、マカッサルには中学校と師範学校があった。オランダ植民地時代から上級学校へ進学できたのはよほどの裕福者や名門の子弟に限られていた。教師と生徒との関係はどこの国でも同じで、生徒がどんなに偉くなってもかつての先生はあくまで先生であり、敬服するものであろう。マカッサル師範学校に管藤ナツ子という女性教師かおり、回教協会へもよく来たが、彼女が終戦後インドネシアへ旅行すると、かつての教え子が軍の司令官、銀行の頭取や官庁・会社の要職についており、彼らがちゃんと手配してくれて、先導車つきで旅が出来たという。教え子の中にはジャワに渡っていた者もおり、大いに歓迎してくれたという。マカッサル中学の校長は本田さんといったが、引き揚げ後の住所が分からず、かつての教え子たちが、やっとの思いで住所を探り当ててインドネシアに招待してくれたという美談がある。
終戦でプワルタ・セレベスは廃刊となり、わたしと近藤編集長と二人でマカッサル郊外のさる民家にしばらく滞在した。そこにマナイ・ソフィアンがしばしば訪れて情報を伝えてくれた。ほどなく、民間人は全部マカッサル北方のマロスというところに収容された。というよりもバラック建てのキャンプで自給生活をしたのである。最初に進駐してきたのはオーストラリア軍兵士を中心とする英連邦軍であった。取り扱いはあまりひどくなかった。ここに、二ヵ月滞在したろうか、その後軍人を含めた全日本人は南セレベス第二の町パレパレの北方のマリンプンという広大な草原に移された。住まいはもちろんバラック建てで、床は竹を割ったのを並べただけのものであった。独身者はこうしたバラックに入居したが、妻子持ちや現地人女性と(結婚)した人たちには別棟が提供された。近藤三郎氏は女医と結婚し女の子を設けていたから、この別棟住まいであったが、しばらくして戦犯容疑でオランダ側に連行されてマリンプンを離れていった。現地人女性と(結婚)した人たちは、その女性を日本に連れて帰らなければならなかったが、聞くところによると、折角連れて来た現地人女性は故郷を恋しがってか、日本の生活になじめなかったかして、大部分は帰国してしまったという。
マリンプンに収容されたわれわれは、いつ日本に帰れるのか予想もつかず、十年ぐらいかかかもしれないと覚悟したものである。マリンプンは大草原で、これといった仕事もなかったから、野菜作りや遠く離れた林に燃料の木を切りに行くくらいが主な仕事であった。穴を掘っても牛乳をうすめたような水しか湧いて出なかったので、これをわかして飲料水とした。セレベスは稲の生産地であったから、主食の米には事欠かなかった。風呂はないから、近くの川で水浴するか例のにごり水をかぶるよりはかなかった。暇をもてあますのでいろいろな遊びが行われた。あらゆ る職業の人が集まっていたから、たいがいな物が作れた。将棋のコマなどやすやすと作る人もいた。演芸会や相撲大会なども行われた。セレベス新聞の記者は短波放送で日本から送信されるニュースを聞き、それを「草原」と題するガリ版刷りのいわば新聞として毎朝みんなに読んで聞かせ喜ばれたものである。終戦で日本はアメリカ軍に占領されたのだから、これからは英語が必要になると考え、わたしは暇を見つけては英和辞典から必要と思われる単語をひろい出し、それをノートに書きとって覚えようとした。これが後日大いに役立った。
いつ帰国できるとも知れず暮らしていたわたしどもに翌年5月に引き揚げできるという朗報が舞い込み、躍り上がって喜んだ。いざ帰国というので或る日のまだ薄暗い早朝、トラックに乗り込んで引き揚げ港のパレパレの町に向かったが、途中オランダ兵にとがめられ、トラックで来るとはけしからん、歩いて行けと命令され、しぶしぶ歩かされた。長い道のりを歩かされたので、道にはそれとわかる汗のしたたり跡が残った。汗の行進であった。できるだけたくさんの物を持ち帰ろうと重いリュックを背負った人などは、パレパレの港に着くや倒れ込む始末であった。行進中現地人はわたしども日本人を好奇のまなざしで眺めていた。これまでの主人であった日本人のあわれな姿に同情したのかもしれない。
パレパレ港から引き揚げ船で出発したのは5月12日であった。引き揚げ船は満員でろくろく足を伸ばして寝られないほどの混みようであった。わたしは何もやることがなかったから、マカッサルで知り合いになった現地人の名を手帳に書き込んだり、ゲートル(脚絆)を刻んで帽子を作ったりした。わたしがゲートルで妙な帽子を作ったのにはみんな驚いたようだ。5月21日の早朝、四日市沖に近付き陸が見えた瞬間、わたしは感激のあまり胸がつまった。同日名古屋に上陸した。上陸するや防疫消毒用のDDT粉を全身にふりかけられたのには参った。名古屋を出発して、それぞれ故郷に向かったわけであるが、戦犯容疑でマカッサルに抑留された近藤三郎氏の妻子の面倒を託された栗城赳君が別れを告げる姿は痛々しかった。
わたしは5月25日に品川駅に到着、その足で毎日新聞社に帰国報告をし、その日は板橋の大山に住んでいた平三郎叔父宅に一泊し、翌26日に上野駅を出発して宇都宮で下車、その足で毎日新聞宇都宮支局を訪れた。支局長はセレベス新聞に勤務したことがあり、わたしと顔見知りの後藤咲郎氏であったのは偶然としか言いようがない。支局は宇都宮裁判所裹の館野石材店の貸家を事務所としていた。支局には同輩の西腰松丘と有働達の両君のほかに名前は忘れたが女性記者がいた。支局次長は鶴池憲氏であった。その日はマカッサルで知り合った宇都宮生まれの小野瀬さんの家に泊めてもらい、翌27日に叶谷の実家に帰った。わたしをかわいがってくれた祖母と父はすでに亡くなっていた。
関連資料
- セレベス新聞時代を顧みて(1)
- セレベス新聞時代を顧みて(2)
- セレベス新聞時代を顧みて(3)
- バンドン会議特派員時代の想い出
- セレベス新聞時代を顧みて(追録)
- Haji Umar Feisal 小林哲夫のこと
- 近藤三郎 セレベス新聞社 「プワルタ セレベス」編集長のこと
注:著者のご了解を頂き「八十年を顧みて」(平成13年10月25日発行)の一部をそのまま転載させて頂きました。(編集部)